2025年は米国経済の減速や金利動向が注目される中、米国株投資に関心を持つ人が急増しています。
この記事では、2025年におすすめの米国株銘柄を初心者向けにわかりやすく解説。
さらに、
まで具体的に紹介します。
- 2025年に注目すべき米国株銘柄
- 高配当株・成長株の特徴と選び方
- 配当利回り比較と投資シミュレーション
- 初心者でも実践できる米国株投資戦略
- 証券口座を使った具体的な投資の始め方
目次
2025年の米国株市場の見通し
- インフレの落ち着きとFRBの利下げ
→中央銀行(FRB)の利下げは、株価上昇につながる
- テクノロジー株を中心に投資マネーが流入
→特に大企業のAI投資など拡大している
- 高配当株は依然として安定志向の投資家に人気
→米国企業は配当比率が高い傾向がある
👉 参考記事:株を塩漬けにしてしまう人へ|株価ではなく企業価値を見よう
米国株おすすめ銘柄【2025年版】
成長株(キャピタルゲイン狙い)
高配当株(インカムゲイン狙い)
👉 関連記事:配当金で月1万円を受け取るには?具体的な方法を解説
高配当株の利回り比較(2025年時点)
| 銘柄 | 配当利回り | 増配実績 |
|---|---|---|
| コカ・コーラ(KO) | 約3.0% | 62年連続増配 |
| ジョンソン&ジョンソン(JNJ) | 約3.1% | 61年連続増配 |
| プロクター&ギャンブル(PG) | 約2.5% | 67年連続増配 |
👉 長期で持つなら「生活必需品 × 増配実績」が強いポイントです。
投資シミュレーション(配当収入の例)
仮に「高配当株3銘柄に合計100万円を均等投資」した場合の配当収入をシミュレーションすると以下の通りです。
👉 配当は再投資することで複利効果が働き、10年後には受け取る配当も増加します。
【実体験】実際に米国株へ投資してみた結果
私が米国株投資を始めたのは2021年3月です。
当時は「将来のために資産形成を始めたい」と考え、いろいろ調べた結果、成長性と安定した配当が魅力の米国株に挑戦してみることにしました。
ここでは、実際に投資した銘柄と2024年の1年間で得られた配当金の結果を公開します。
(日本株も一部保有しているため、そちらも合わせて紹介します。)
保有銘柄と運用結果(2024年12月末時点)
①国内株式の運用結果
| 銘柄コード | セクター | 銘柄 | 保有数量 | 配当金(年間) |
|---|---|---|---|---|
| 2236 | その他 | GXUS配当貴族 | 3 | 125円 |
| 9434 | 通信 | ソフトバンク | 2,000 | 12,900円 |
| 8306 | 銀行 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 4,550円 |
②米国株式の運用結果
| 銘柄コード | セクター | 銘柄 | 保有数量 | 配当金(年間) |
|---|---|---|---|---|
| T | 無線通信サービス | AT&T | 70 | 27.9$ |
| AAPL | 電話&携帯端末 | アップル | 15 | 6.61$ |
| XOM | 総合石油&ガス | エクソンモービル | 50 | 141.46$ |
| WBA | 医薬品の小売 | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 21 | 15.12$ |
| KO | 清涼飲料水 | コカ・コーラ | 25 | 32.76$ |
| SPYD | ETF | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 120 | 182.11$ |
配当金の実績まとめ
- 国内株式の配当金合計:17,575円
- 米国株式の配当金合計:405.96ドル
(1ドル=152円で計算 → 約61,705円)
👉 年間合計配当金:79,280円
投資額と利回り
2024年末時点での投資額は約260万円。
そこから得られた年間配当は約3%の利回りでした。
実際に投資して感じたこと
このように、米国株投資は「配当を受け取りながら長期で育てる」という実感が持てる投資だと感じました。
投資初心者が意識すべき戦略
👉 参考記事:新NISA完全解説!初心者が知るべきポイント
米国株投資を始めるなら
米国株に投資するには、国内証券会社の口座開設が必要です。
初心者におすすめの証券会社は以下の2つです。
- SBI証券:取引銘柄数が豊富で手数料も安い
- 楽天証券:アプリが使いやすく、投資初心者でも安心
👉 SBI証券の口座開設はこちら
👉 楽天証券の口座開設はこちら
まとめ
2025年の米国株は「AI関連の成長株」と「安定した高配当株」の二極化が進むと予想されます。
投資初心者は無理のない範囲で分散投資し、長期目線で保有することが大切です。
👉 関連記事:安定収入を目指す投資戦略を徹底解説
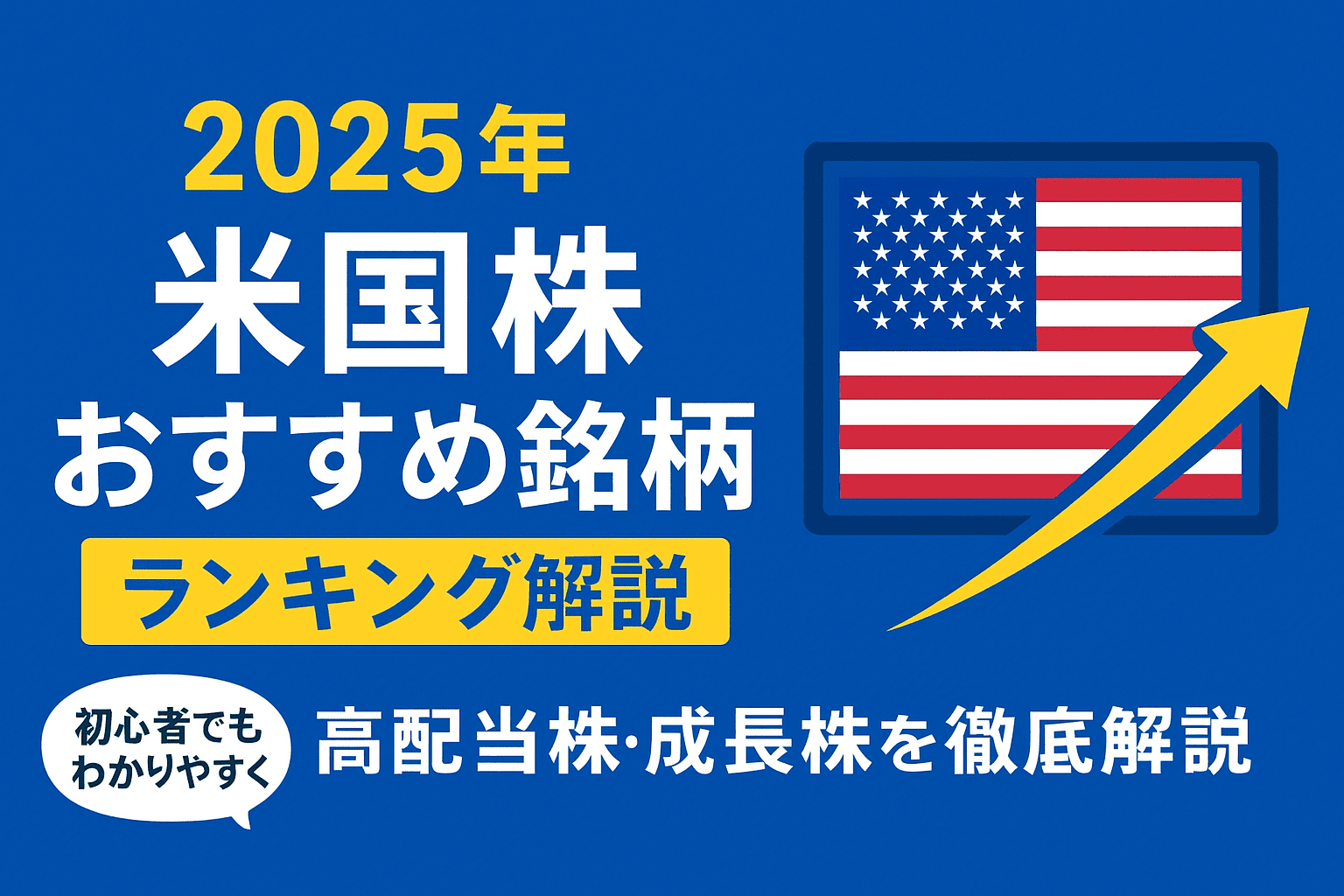
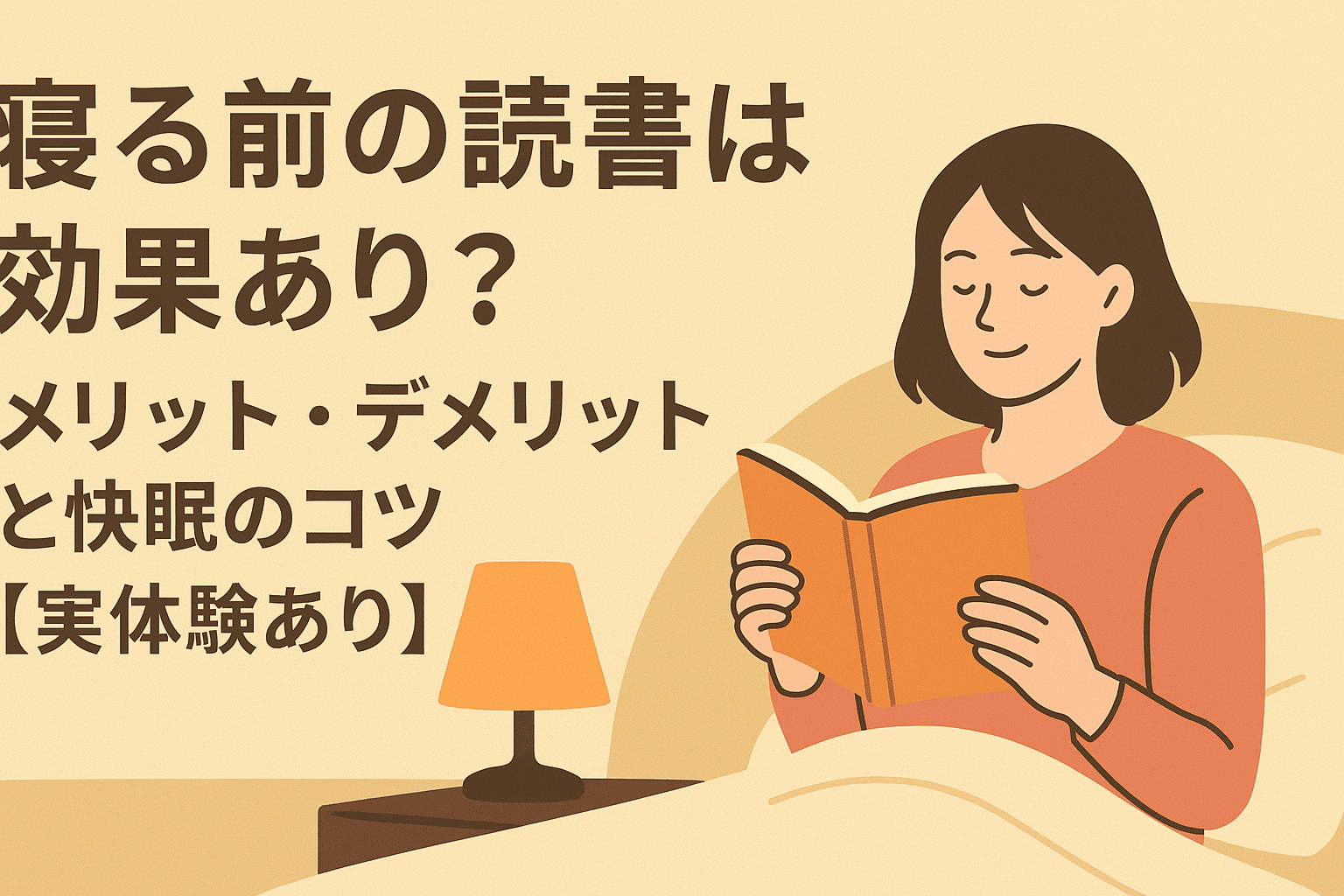
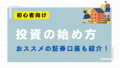
コメント