アメリカの大統領選挙でトランプ氏が当選して、早2か月が経過しようとしています。
今回は「米国株式」をメインにした記事になっています。
新NISA制度からちょうど1年が経過しようとしていて、最近投資スタートさせた方も多いのではないでしょうか?
そこからさらに視野を広げてみて、
・米国株式投資って何がいいのか?
・投資するメリットはあるのか?
・どうやって投資先を選ぶのか?
このような疑問について、投資初心者の方でも分かるように詳しく解説しています。
また最後に、私が米国株式に今年1年間投資して得られた利益についても記載していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
米国株の特徴6選
主な米国株の特徴を6選ピックアップしました。まずは特徴を押さえて、日本と米国との違いを理解しましょう!
①多様な企業と業種
米国株市場は、非常に多くの企業と業種が存在しており、特にテクノロジー、金融、消費財、エネルギー、ヘルスケアなど、世界的に影響力のある企業が多数上場しています。
代表的な企業には、Apple、Amazon、Microsoft、Teslaなどがあります。

一度は聞いたことがある有名な企業ですよね!
日本という島国にまで範囲を大きく広げているのは、米国企業の特徴と言ってもよいでしょう。
ちなみに、2024年現在の米国の主な株式市場に上場している会社数は非常に多いです。
ちなみに、米国には大きく2つの株式市場があります。
①ニューヨーク証券取引所(NYSE)
約2,400社以上の企業が上場しています。
②ナスダック(NASDAQ)
約3,300社以上の企業が上場しています。
①②を合わせて約5,700社が上場しています。
それに対して、日本の株式市場には東京証券取引所があります。
東京証券取引所(TSE)には、約3,700社程度が上場しています。(プライム、スタンダード、グロース市場を含めたもの)
つまり、日米の企業の上場数には約2,000社ほどの差があります。
日米の上場基準には差がある
日米の上場数には約2,000社の差があると書きましたが、実は日米では上場するための基準が違います。
国ごとの価値観や法律によって、細かく見ると異なる点は多いですが、大まかに以下の点が異なります。
日本の東京証券取引所では、上場基準が厳格で、特に企業の財務健全性や利益を重視する傾向があります。
つまり、その企業の実態=「財務」を重視しているということですね。

この会社はしっかり利益出してるし、基準もクリアしているから上場してもよし!
このような基準で上場するかどうかが決定されます。
ニューヨーク証券取引所やナスダックなどの米国の主要取引所は、比較的明確で透明な上場基準を持っていますが、上場基準が「厳格」というよりも「柔軟性の高さ」が目立ちます。
企業は一定の資本や利益を示さなくても、上場できる場合があります。
つまり米国の上場基準では、その企業の「将来性」を重視していると言えます。

この会社は業種的にも需要があるし、成長のポテンシャルあり!
上場基準はまあまあだけど上場してもよし!
このような感じです。
少し甘さもありますが、柔軟に会社を見て判断されます。
②安定した市場の規模
米国株市場は世界で最も規模が大きく、流動性が高いです。
ニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダック(NASDAQ)などの主要な取引所で取引される株式は、世界中の投資家にアクセスされており、資金調達のための市場としても重要な役割を果たしています。
特にナスダックでは、利益が出ていない段階の企業や、将来性が高いと見なされるテクノロジー企業、スタートアップ企業の上場を積極的に受け入れています。
成長段階の企業が上場して資金調達を行うことは一般的です。
これは日本の上場基準とは、逆であることがわかります。
日本の場合は、しっかり利益が出ている企業を上場させています。
しかし、米国ではIPO(新規公開株式)の段階で、企業が必ずしも利益を出していなくても、将来性のあるビジネスモデルや市場の需要が重要視されます。
このように、米国企業は比較的資金調達をしやすい環境が整っています。
それが、安定した市場を実現させています。
③テクノロジー企業の影響力
特に近年では、テクノロジー企業の影響力が大きいです。
例えば「FAANG」と総称されている...
・Facebook(Meta)
・Amazon
・Apple
・Netflix
・Google(Alphabet)
これらの企業は、株式市場全体のパフォーマンスに大きな影響を与えることが多く、市場動向を左右する要因となります。
特に、イノベーションの発端となっている企業が、米国に集中しています。
これは、日米の上場基準のところでも触れましたが、米国市場は「柔軟性」を重視しています。
日本の場合は、昔からの技術や事業をもっと洗練させて、誰にもまねできないレベルにまで引き上げることに長けています。
対して米国は、異業種の技術や考え方を柔軟に、取り入れて組み合させることで、世界にまだない新しい技術やサービスを生み出しています。

これがイノベーション(技術革新)と呼ばれています!
例えば、今では広く普及している「サブスク」というサービスがあります。
この発端は、現在では名前を知らない人はいないであろうNetflixです。

元々は、新聞や雑誌の定期購読から始まりましたが、それをサブスクリプションモデルという新しい形態として普及させたのはNetflixです。
インターネットを利用した映像コンテンツのサブスクリプションサービスを早期に導入し、1997年に設立されたNetflixが、2007年にオンラインストリーミングサービスを開始することで、世界中に広く普及していきました。
今では多くの企業が真似をして、このようなビジネスモデルで収益を確保しています。
このように、イノベーションの発端である企業が米国企業に集中しているので、米国の株式指標(NYダウやS&P500など)は世界の景気を表しているともいわれるわけです。
④高い流動性
米国株は、世界中で取引されているため、「流動性」が非常に高いです。
これにより、投資家は必要なときに株式を売買しやすく、取引のコストも比較的低いことが特徴です。
日本の場合、ある会社の株式を購入しようとすると「100株単位」が基本です。
つまり、1株1,000円の株式を購入するためには、100,000円(1,000円×100株)が必要になります。

しかし、米国は1株単位から購入が可能です!
つまり1株1,000円の株を1株だけ購入することも可能です。
つまり1,000円あれば株式投資が可能というわけです。
これは米国株の株式数が数多く発行されているため、投資家は比較的安い価格から購入することができます。このことを「流動性が高い」と言います。
流動性が高い会社の株式の方が、多くの投資家の方から購入してもらえますし、企業側からすれば分散投資していることになりますよね。
もう少し深く踏み込んでみると、流動性が高い理由は、時価総額が高いこととも関係しています。
時価総額とは、その会社の総体的な価値を意味します。基本は、「株価×発行株式数=時価総額」になります
AppleやAmazonなどの大きな米国企業では、1株当たりの価格ももちろん高いですが、発行している株式数も多いです。
つまり、株式数を増やして世界中の投資家から購入してもらうことで、資金調達にもなりますし認知度もあがりますよね。
まとめると、米国企業は高い流動性から、世界中の投資家から認知してもらって資金を集めています。
⑤規制と透明性
米国株市場は、アメリカ証券取引委員会(SEC)などの規制機関によって厳しく監視されています。
企業は定期的に四半期ごとの決算報告を行い、投資家はこれに基づいて意思決定を行います。
この透明性と情報公開が投資家にとって大きな利点となります。
「証券取引委員会」を意味します。簡単にいうと、米国の株取引などの証券取引を監視・監督しています。
なぜこのような組織が存在しているかというと、証券市場の公平性を担保することで、投資家を守るためです。
SECが設立された背景としては、1929年の世界恐慌後に、証券会社の不正が次々と発覚したからです。
その不正を監視するためにSECができたというわけです。
このようなSECの存在が、米国の証券市場の公平性を保っていることもあり、不正による株価変動などが起きないように未然に防いでいます。
⑥高い配当利回り
こちらは投資家の皆さんにとって、一番のメリットとなる特徴だと思います。
米国企業の中には、安定した収益を上げている企業も多く、高い配当利回りを提供する企業もあります。
特に、ディフェンシブ銘柄(消費財や公社関連株など)は安定した配当を支払う傾向があります。
上記の特徴を①~⑤までをおさえると、米国の株式市場は底堅い土台がしっかりと整備されています。
さらにテクノロジー企業などが多いことから、まだまだ大きくなると予想できます。
そのようなしっかりとした基盤の中で、米国企業は利益を生み出し続けています。
その利益を、しっかりと配当金という形で投資家へ還元してくれているのも米国企業の特徴の1つです。
米国株投資のメリット
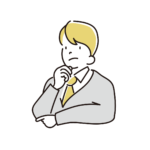
米国株投資の一番のメリットは何なのか?
1番のメリットとしては、「高い配当利回り」です。
私は米国株に5年ほど投資を行っていますが、自分でも驚くほどの配当金が入ってきました。
日本株と比較して、高配当株投資の違いについてご説明しますね。
米国はETFが多数存在する
日本との1番の違いは、ETF(Exchange Traded Fund)が多数存在していることです。
ETFとは、上場投資信託を意味します。
通常の投資信託は上場していないので値動きは1日に1回。しかし、ETFは株式等と同じく上場しているため取引時間内は常に価格が変動します。
つまりETFは、投資信託のメリットである分散投資と、株式のメリットであるリアルタイムで価格変動する2つのメリットが合わさったものです。
米国株に個別投資しようとすると、多数の銘柄の中から何に投資するか選択しなければいけません。
しかしETFであれば、高配当株を幅広く分散して保有できるので、銘柄選択の手間が省けます。
例えば500種類もの高配当株を含むETFに投資することで、かなりの企業に分散投資している状態にできます。
米国ETFの大きな特徴は以下の3つになります。
①定期的に組入銘柄の入れ替えがある
米国高配当ETFは、年1回銘柄の入れ替えを行います。
これはある基準に満たない銘柄を除いて、基準を満たしている他の銘柄へ入れ替えを行います。
もし入れ替えがなければ、配当が徐々に下がって衰退している企業に投資し続けることになるので、投資家のメリットが損なわれます。
それを防ぐためにも、定期的に組み入れ銘柄を入れ替えて、高配当を生み出せるETFを実現させています。
②手数料が安い
ETFを購入して売却するまでには、大きく2つの手数料が発生します。
株式購入の場合と比較してみましょう。

ETFの場合は、保有時に「信託報酬」という手数料がかかります。
投資家がETFを保有している期間に、ETFの残高に対してかかる手数料になります。これは、ETFを管理・運用してもらう運用会社に支払う手数料になります。
つまりETFは、保有時にも手数料がかかるということを覚えておいてください!
しかし、それほど心配する必要はありません。
なぜなら、かかる手数料は微々たるものだからです。
以下のサイトは、米国のインデックスファンド、ETFのランキングになります。
https://myindex.jp/ranking_f.php?s=1&a=31
このランキングの信託報酬の欄を見ても分かるように、「約0.03∼0.08%」ほどの手数料がかかります。
日本の投資信託を保有している場合にかかる信託報酬については、「約0.96%」です
投資信託協会のデータ「公募株式投信(追加型)における運用管理費用(信託報酬)の推移」によると、追加型の公募株式投資信託の信託報酬率の平均は、2024年7月末現在で「0.96%(税抜)」でした。
引用:https://www.toushin.com/q&a/average-management-fees/
まとめると、米国ETFを購入して保有していても、それほど手数料については気にしなくてもよいということになります。
③流動性の高さと取引の柔軟性
米国ETFは取引所に上場しているため、株式のようにリアルタイムで売買できます。
取引時間内であれば、いつでも取引できるため、投資家は柔軟にポートフォリオを調整できます。
また、多くのETFは非常に高い取引量を誇り、流動性が高いため、スムーズな売買が可能です。
ETFの大きな特徴が、この「リアルタイムで取引できるかつ、分散投資できる」点です。
例えば、まだ投資するのに大きな元手資金がない方だと...

投資したいけど、いきなり個別株だけに投資するのは怖いな...
でも他の株を購入する資金もないしな...
このような悩みが大きいと思います。

そんな時こそETFの出番です!
株のようにリアルタイムなので、購入・売買する自由も効きますし、様々な銘柄に分散投資を行えます。
2024年の米国株投資の結果
現時点での私が保有している米国株・ETFのポートフォリオを公開します。
また、約1年でどれほどの配当金が入ってくるのかも参考までに記載します。
※日本株式も少し保有しているので、その結果も記載します。
【国内株式】
| 銘柄コード | セクター | 銘柄 | 保有数量 | 配当金(年間) |
|---|---|---|---|---|
| 2236 | その他 | GXUS配当貴族 | 3 | 125円 |
| 9434 | 通信 | ソフトバンク | 2,000 | 12,900円 |
| 8306 | 銀行 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 4,550円 |
【米国株式】
| 銘柄コード | セクター | 銘柄 | 保有数量 | 配当金(年間) |
|---|---|---|---|---|
| T | 無線通信サービス | AT&T | 70 | 27.9$ |
| AAPL | 電話&携帯端末 | アップル | 15 | 6.61$ |
| XOM | 総合石油&ガス | エクソンモービル | 50 | 141.46$ |
| WBA | 医薬品の小売 | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 21 | 15.12$ |
| KO | 清涼飲料水 | コカ・コーラ | 25 | 32.76$ |
| SPYD | ETF | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 120 | 182.11$ |
結果としては...
・国内株式の配当金合計額は、「17,575円」
・米国株式の配当金合計額は、「405.96$」
・米国株式は為替の関係で多少変動はしていますが、2024年の年間平均である1$=152円で計算すると、日本円で「約61,705円」です。
全ての配当金の合計額が、「79,280円」になりました。
現在約260万円ほど株式投資で運用していますが、年間「約3%」の利回りという結果になりました。
その他にも、銘柄入れ替えで株式を売却したりと、そのほかの利益も出ていますが、今回は配当金額のみにフォーカスしました。
私の場合は、入金された配当金もそのまま運用に回しているため、投資金額もそれに合わせて増加しています。
そうすることで、結果さらに配当金も増えていくことになります。

このような仕組みを「複利」と呼びます。
NISAの成長投資枠である1,200万円まで、まだまだ届いていないためこの上限枠いっぱいを目指して投資を継続していきます。



コメント