目次
リスクとリターンを理解する重要性
投資を始める際に必ず避けて通れない「リスクとリターン」の関係について、この2つは投資の土台として、必ず理解して多く必要があります。
リスクとリターンの関係性
投資を行うときに真っ先に想像することが「リターン」ですよね。
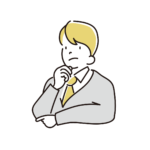
投資したらどれくらい儲かるかな?
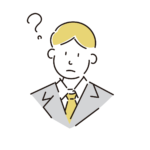
利益が出そうな商品はどれか?
投資の目的はリターンを得ることなので、真っ先に思い浮かぶことについては納得です。
しかし、このリターンと同じくらい重要なのが「リスク」です。
リターンとリスクはトレードオフの関係となっているので、決して切り離せないものになっています。
高いリターンをリスクなしで得ることができるのなら、すでに皆さんはお金持ちになって積極的に投資を行う意味はありませんよね。
リスクを低くすれば、逆にリターンも低くなります。
つまり、リターンとリスクはトレードオフという関係になります。
トレードオフとは?
1つの選択をすることで得られる利益と、それを選択しなかった場合に失われる損失との間のジレンマを指す経済学用語。
ある選択を追求することで、ほかの選択を放棄する必要が生じる状況を指します。
投資においてリスク管理は重要
リターンと合わせて重要であるのが「リスク」です。
初心者が投資を始められないケースの多くが、このリスクに恐怖心を持っているからです。
会社から給料をもらって、それを貯金しておけば少なくとも損をすることはありません。
しかし、投資をして利益を得ようとなると、やはり損をするリスクというのは避けられません。
初心者の方は、このリスクを過剰に気にすることで、投資スタートの機会を逃しています。
ここで投資に踏みきれない、あるいは口座開設まではしたものの何も購入できずにいる方にお伝えしたいことがあります。
この過剰な恐怖心を生み出しているリスクは、自分で管理することで最小限に抑えることができます!
リスク管理をしっかり行うことで、リターンを狙いつつリスクを最小限に抑えるということが可能です。
なので、先ほどのトレードオフの弱点「他の選択を放棄する必要が生じる」ことを克服できます。
決して、リスクを完全にゼロにできると言っているわけではありません。
リスク管理することで、そのリスクを最小限に抑えることができるものという認識を持ってほしいのです。
トレードオフでは、「他の選択を放棄する必要が生じる」と説明されていますが、放棄するのではなく管理すればよいのです。
その管理方法をご説明していきます。
リスクとは?投資におけるリスクの種類
リスクの意味について、リスクの種類について説明します。
この部分が明確になっていないと、投資するときとその後の運用面で心理的に悪い方向に影響してしまいます。
リスクとはいったい何なのか?
リスクという言葉を聞くと、真っ先に何が思い浮かびますか?
「損する可能性が高い」「危険性がある」などとイメージすることが多いのではなでしょうか。
リスクの意味を調べると、「危険度や予想通りにいかない可能性」と表示されます。
この予想通りにいかない可能性とはどういうことか?
例えば...

将来私は野球選手になりたい!
このような夢を想像していることは、将来確実に起きるとは限りませんよね。
これもリスクの1つと言えます。
逆に...
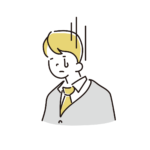
将来、私はホームレスになるかもしれない...
このように思うことも確実性がないので、リスクと言えます。
つまり、リスクとは将来どうなるか分からないことを指します。
投資のリスクについて考えると、損をするかもしれないが利益が出るかもしれないということです。
しかし、「リスクがあるってことは損をするってことだ!」と勝手にイメージが独り歩きして、過剰に恐怖心を生み出しています。
つまり、リスクとは「将来どうなるか分からないこと」という意味です。
ここでリスクの意味をしっかり意識に刻んでください!
具体的にどんなリスクがあるのか?
投資を行うにあたって、どんなリスクがあるのか?
そのリスクの種類と、そのリスクが投資結果に与える影響について解説していきます。
①市場リスク
「市場リスク」とは、株式や債券などの金融商品が、経済の状況や市場全体の動きに影響されて価格が上下するリスクのことです。
簡単に言うと、市場全体の動きが原因で投資している商品の価格が下がったり、逆に上がったりする可能性があるということです。
例えば、皆さんが個人で株式を購入している場合、その企業の業績やニュース、商品やサービスの成功などで株価が上がります。
逆に、市場全体の状況が悪い場合があります。
例えば景気が悪化したり、政治的な問題や自然災害・戦争などが起きたりすることが影響して株価が下がることがあります。
このような価格の変動は、私たちが直接コントロールできない外部要素によって引き起こされます。
②信用リスク
「信用リスク」とは、投資先の企業や発行体が財政的な問題を抱え、約束した支払い(例えば、利息の支払い・元本の返済など)ができなくなるリスクのことです。
特に、企業の債券や借入を行っている場合、このリスクが直接的な影響を与えることがあります。例えば、ある企業の発行した債券を購入したとします。
もしその企業が経営不振に陥った場合、支払い能力が低下し、債券の利息を支払えなくなることがあります。
最悪の場合、企業が倒産してしまうと、投資のリターンが大きく低下したり、投資をした私たちの元本が失われる可能性もあります。
③流動性リスク
「流動性リスク」とは、投資した資産を、希望するタイミング・価格で売却できないリスクのことです。
言い換えると、市場でその資産を素早く現金化できない可能性です。
流動性リスクが高い場合、売りたいときに売れず、あるいは価格が大きく値下がりしてしまうことがあります。
例えば、ある企業の株を購入したものの、その株式の取引量が非常に少ない場合...
その株を売りたくても市場に十分な買い手がいないため、売却できないことがあります。
また、売却できたとしても、予想していた価格よりもかなり低い価格でしか売れないことがあります。
④金利リスク
「金利リスク」とは、金利の変動が投資の価値やリターンに影響を与えるリスクのことです。
特に、債券やローンなど、金利と密接に関連する金融商品でよく見られます。
金利が上昇したり下降したりすることで、投資商品の価値や利回りが変動するため、投資結果に大きな影響を与えることがあります。
例えば債券の場合だと、利率5%の債券を購入したとします。
金利変動で利率が6%に上昇すると、新たに金利6%の債券が発行されます。
すると保有している5%債券は、6%債券と比較して魅力が落ちてしまうので、5%債券の価格は価値が下がってしまいます。
また、住宅ローンや借り入れの場合、金利上昇する子で、支払うべき利息がその分増えることになります。
このように自信の投資結果にも影響を与える可能性があります。
リターンとは?投資による利益の仕組み
リターンとは具体的に何を指すのか?
リスクと密接に結びついているのがリターンで、リスクと同様に正しく理解しておく必要があります。
リターンとは?
リターンとは、投資で得られる利益のことです。
言い換えれば、「投資したお金がどれだけ増えたか」を示すものです。
リターンは、投資を通じて得られる収益や利益のことを指します。
例えば、「私の得たリターンは年間で10%です」という意味合いです。
リターンは通常、「元本に対してどれだけ利益が出たか」を計算します。
上記の計算方法としては、100万円を投資して1年後に10万円の利益が出た場合、そのリターンは「10%」になります。
つまり、年間で10%のリターンとなります。
リターンは、自分が投資したお金がどれだけ増えたか(または減ったか)を示すものです。
リターンを計算することで、どれだけ利益を上げたかがわかり、投資の成果を評価できます。
投資を始めたばかりでも、どのくらいリターンが変動しているかを認識しているかを把握しておく必要があります。
そのため、リターンについて正しく理解しておくことは、非常に重要です。
リターンの種類
リターンには大きく2種類あります。その利益による違いを解説していきます。
リスクがあるからこそリターンがある
投資の基本原則として、「リスクがあるからこそリターンがある」という考え方があります。
これは、リスクを取らないと、リターン(利益)も得られない、という意味です。
たとえば、安全な銀行預金ではお金がほとんど増えませんが、株式投資などリスクのある投資では、うまくいけば大きなリターンを得ることができます。
この「リスクがあるからこそリターンがある」という基本原則を理解することは、投資をする上で非常に重要です。
リスクを取らなければ、リターンも得られません。
しかし、リスクを管理しながら投資をすることで、リターンを得る可能性を高めることができます!
リスクとリターンのバランスをどう取るか?
リスクとリターンの基本的な意味を把握できたところで、この2つのバランスをどうとっていくのか実践的な内容をお伝えします。
リスクとリターンは密接に関連しているため、リターンを得るためにはリスクを取る必要があります。
その際に、どれくらいのリスクを取るかが投資家にとって、とても重要です。
自分のリスク許容度を知る
まずは、自分がどれくらいのリスクを許容できるかを把握します。
自分がどれくらいのリスクを取れるか、つまり資産が減る可能性をどれだけ受け入れられるかということを把握していきます。
ここが明確になっていないと、投資を行う際に迷いやが生じてしまい、資産が減る可能性が高まってしまいます。
初心者が自分のリスク許容度を知る方法を解説していきます。
投資目的を明確にする
投資を始める前に、まず自分の投資目的を考えましょう。
投資の目的は人それぞれ異なります。
例えば、短期的な利益を追求するのか、長期的に資産を増やすことを目指すのかによって、取るべきリスクも変わります。
大きくは以下の2つから、自分はどちらが合っているのかを選択してください。
●長期的な目標(例えば、退職後の資産形成)を目指す場合
比較的リスクを取る余地があります。
●短期的な目標(例えば、数年後の大きな支出のため)を目指す場合
リスクを抑えた投資が適しています。
目的に応じて、リスクをどれだけ取れるかが変わります。
投資経験と知識を評価する
リスクを受け入れるかどうかは、自分の投資に対する知識と経験にも影響されます。
当然初心者の方は、投資に関する知識や経験が少ない分、リスクの大きい投資に対する不安感が強くなるかもしれません。
これは、投資経験が知識がないとだめ!と言っているわけではありません。
自分の状態を客観的に評価して、リスクが取ることに対する抵抗感を判断しています。
なので、ここではリスクに対する抵抗の感度を自信で把握してもらえるだけで十分です。
生活の安定性を考慮する
自分の現在の生活の安定性を見直してみましょう。
仕事や収入の安定性、家庭の状況(例:扶養家族の有無)によって、リスクを取れる余裕が変わります。
まずは自身の年齢では、どのくらいの投資を行っているのかを把握することが重要です。
以下の三菱UFJ銀行が掲載している「年代別で考える資産運用」を確認して、年代ごとのライフイベントなども含めて詳しく解説してありますので、参考にしてみてください。
年代別で考える資産運用_三菱UFJアセットマネジメント
リスク許容度アンケートを実施する
以下のサイトから、無料でリスク許容診断テストが実施できます。
あなたのリスク許容度診断テスト_一般社団法人全国銀行協会
これらの質問に答えることで、自分のリスク許容度を客観的に見極めることができます!
投資額を決める
リスク許容度は、投資する金額にも影響されます。
例えば、自分にとって大切な生活資金を全額投資に回すのはリスクが高すぎます。
リスク許容度を測るために、投資額を「生活に支障をきたさない範囲」に設定しましょう。
ちなみに私は投資を始めたときの初期投資額が50万円でした。
銀行預金が約100万円ほどあり、その半分を投資に回しました。
私自身20代独身で、他に預金の使い道もなかったのでこの額に設定しましたが、家庭や金銭状況によって、皆さん異なると思います。
あくまで、余剰資金で行ってください!
生活資金まで入れてしまうと、万が一の場合に生活が困窮してしまう可能性があります。
余剰資金で投資を始めることが、安全に投資を続けるための第一歩です。
リスクを抑えるための実践的な投資戦略
ここからは、リスクを抑えるための投資戦略について解説します。
戦略を把握して投資を行うのと行わないとでは、リスクとリターンともに大きく影響します。
まずは、代表的な投資戦略を理解しましょう!
分散投資
リスクを分散させるためのポートフォリオの組み方を解説していきます。
分散投資とは?
分散投資とは、1つの投資対象に全てのお金を投じるのではなく、複数の異なる資産に分けて投資することです。
例えば、株式、債券、不動産、商品(ゴールドや原油など)など、異なる種類の資産を組み合わせることで、リスクを減らし、安定したリターンを目指す方法です。
「リスクを分散する」と聞くと、なんとなく安心感が湧いてきますよね。
実際、分散投資はリスク管理の最も基本的な戦略の一つです。
どのように分散投資を実践するか?
分散投資を実践する方法は、主に以下の3つの方法が一般的です。
(1) 資産クラスの分散
資産クラスとは、株式、債券、不動産、商品など、投資の対象となるカテゴリのことです。
これらはそれぞれ異なるリスクとリターンの特徴を持っており、例えば株式市場が不安定な時期でも、債券市場が安定している場合もあります。
資産クラスを分散することで、リスクをさらに減らすことができます。
(2) 地理的な分散
地理的な分散とは、異なる国や地域に投資を分けることです。
例えば、国内の株式だけに投資するのではなく、アメリカやヨーロッパ、新興国の株式にも投資することで、特定の地域の経済状況によるリスクを避けることができます。
私自身も投資額のおよそ6割を米国へ投資しています。残り4割は日本株です。
米国投資を多めに設定しているのは、リスク分散と合わせて、米国成長からのリターンも狙っているからです。
特に、グローバル化が進む現代では、地理的な分散は非常に効果的な戦略です。
(3) 業種や企業の分散
投資対象となる企業の業種や規模においても分散を図ることが重要です。
例えば、テクノロジー株ばかりに投資するのではなく、消費財、ヘルスケア、エネルギー、金融など、さまざまな業種に投資をすることで、一部の業種が低迷した場合でも、他の業種が安定したリターンを提供してくれる可能性があります。
私も業種分散の観点から、鉄鋼、自動車、金融、IT、エネルギー、食品業など、幅広く分散してあります。
ドルコスト平均法
リスクを抑えながら長期的に安定したリターンを目指す方法を紹介していきます。
ドルコスト平均法とは?
例えば、毎月1万円を株式や投資信託に投資するという形です。
この方法では、市場の価格が高い時も低い時も気にせず、一定のタイミングで一定額を投資します。
この戦略の大きなポイントは、投資金額が一定であるため、購入する株数や投資信託の単位数が、相場の動きによって変動することです。
市場が下落しているときは多くの株を買い、逆に市場が上昇しているときは少なく買うことになります。
ドルコスト平均法のメリット
メリットは大きく3つあります。
ドルコスト平均法のメリット
①タイミングを気にせず投資できる
②平均購入単価を抑えやすい
③リスク分散になる
一定のタイミングでの購入なので、投資タイミングを気にせず投資できます。
これにより「今は買い時か?」などの悩みから解放されます。
また、購入単価が自然に平均化されるため、「高値掴み」を避けることができます。
これは、投資額を変えずに一定して購入するため、自動的に価格が高いときは少なく、価格が安いときは多く購入することができるからです。
そして、長期的にみるとリスク分散になります。
購入タイミングを一定にしているので、価格変動の影響を受けにくいです。
これはいわゆる、時間軸を利用した分散投資法と言えます。
初心者向け投資信託:少額から分散投資できる投資信託やETF(上場投資信託)のメリットを解説。
ドルコスト平均法の実践方法
ドルコスト平均法を実践するためには、まず投資の目的と金額を設定することが大切です。具体的には以下の手順で進めていきます。
(1) 定期的な投資額を決める
まず、自分が毎月投資できる金額を決めます。
例えば、月に1万円、3万円、5万円といった金額を設定します。
これは先ほどご説明した「4. リスクとリターンのバランスをどう取るか?」の「⑤投資額を決めよう」で決定した投資額を参考にします。
投資額を年間の12カ月で割って、月々の投資額を決定しましょう。
最も大事なのは、自分の生活に支障をきたさない範囲で無理なく投資を続けられる金額を選ぶことです。
(2) 投資対象を選ぶ
次に、ドルコスト平均法を実践するための投資対象を選びます。
株式、投資信託、ETF(上場投資信託)など、さまざまな投資先があります。
自分のリスク許容度に応じて、成長性のある企業の株式や、低リスクな債券型の投資信託などを選びましょう。
年齢が20から30代の方には、株式か投資信託の保有をおすすめします。
これは、年齢的にまだ将来働ける時間が多いことが理由です。
以下に投資信託と株式どちらが合っているのか詳しく知りたい方向けの記事があるので、ぜひ参考にしてみてください。
投資信託 vs 株式投資:初心者に最適な選択を見つけるための完全ガイド【2025年最新】 | とむろぐ
(3) 定期的に積立投資を行う
毎月決めた金額を、選んだ投資先に積み立てていきます。
証券会社や銀行の積立投資サービスを利用すると、自動的に投資が行われるので、非常に便利です。
私の場合は毎月、会社からのお給料のうち3万円を投資に回すと決めて、給料日に証券会社へ3万円を入金しています。
私は個別株式の取引きが多いので、日本株式は100株単位からが基本なので、株式購入額がある程度貯まったら、購入に充てています。
また、米国株式の場合だと1株単位から購入できるので、分散投資も兼ねて1株当たりで様々な業種の企業に投資しています。
(4) 長期的に投資を続ける
ドルコスト平均法は、短期的な投資ではなく、長期的な投資戦略です。
数ヶ月、数年というスパンで投資を続けることで、購入価格の平均が適切に調整され、安定したリターンが期待できます。
まとめ
結論としては、リスクとリターンを理解して賢く投資を始めましょう!
特にリスクについては、言葉の意味が独り歩きして、危険を感じさせるものというイメージになっています。
再度お伝えしますが、リスクは「不確実性」を意味しています。
また、投資はどうなるか分からないリスクがあるが、その管理を行うことはできます。
リスクに対して慎重になることはもちろん大事ですが、過度に意識しすぎて投資すらできないというのは本末転倒な気もします。
なので、まずはリスクとリターンの関係をしっかり理解して、投資する商品の中身を自身で確認しましょう。
自分で確認したうえで、今の自分の金銭状況ならこのくらいのリスクなら大丈夫だなと判断してください。
他人やネットの情報をうのみにして、この商品は良いとおススメされているから、というだけで、投資を行うことの方がリスクが高いです。
自分の知識、経験アップも兼ねて、リスク管理を行っていきましょう。
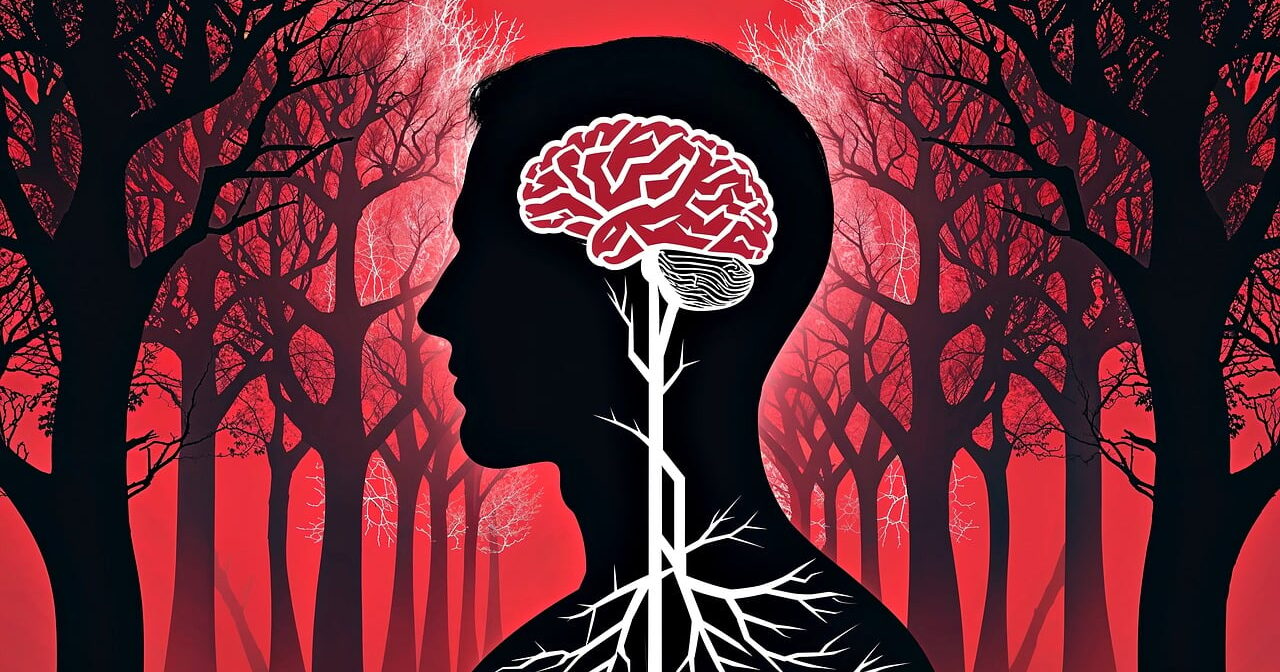


コメント