「投資ってもう遅いんじゃ…?」と思っていませんか?
安心してください。実は、今からでも十分チャンスはあります。
特に新NISAを使えば、税金の優遇を受けながら、少額からでも賢く資産形成を始められます。
この記事から分かること
- 新NISA制度の基本とメリット
- 投資初心者におすすめの始め方(個別株よりインデックス投資が安心な理由)
- 今このタイミングで投資を始めるとよい理由
- 米国株を含めた投資のポイント
- 初心者でもわかる具体的な銘柄例
- 少額で始めた場合のシミュレーション例
- SBI証券・楽天証券で口座を開設する方法
目次
新NISAってそもそも何?
新NISAは2024年1月からスタートした制度で、投資の非課税枠が増えたり、期間が長くなったりしています。
これにより、投資デビューのハードルがぐっと下がりました。
初心者におすすめの投資スタイル
口座は開設したけど、「何に投資すればいいの?」という人が多いはず。
そんなときはまず インデックス投資 がおすすめです。
インデックス投資と個別株の違い
- 個別株
→ 1社ずつ選ぶ必要があり、値動きのリスクも大きい
- インデックス投資
→ いろんな企業にまとめて投資できるため、リスクが分散される
特におすすめのインデックス銘柄例
| 銘柄 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| S&P500連動ETF(例:VOO、SPY) | 米国の大型株500社に分散投資 | 長期的に安定成長が期待できる |
| 全世界株式インデックス(例:VT、オルカン) | 世界中の株式に分散 | 米国以外も含めてリスク分散が可能 |
| 日本株インデックスETF(例:TOPIX連動) | 日本株全体に投資 | 円建てで始めやすい |
少額からの投資シミュレーション
例えば、毎月1万円ずつS&P500連動ETFに積み立てた場合のシミュレーションです(利回り5%/年想定、20年間積立)。
| 積立額 | 期間 | 想定利回り | 予想資産額 |
|---|---|---|---|
| 月1万円 | 20年 | 5% | 約408万円 |
| 月2万円 | 20年 | 5% | 約816万円 |
| 月3万円 | 20年 | 5% | 約1,224万円 |
※実際の運用結果は変動しますが、少額でも長期で積み立てることで複利の効果が期待できます。
今だから投資のチャンス?米国株の注目ポイント
投資を始めるなら、米国株もチェックしておくといいです。
理由はざっくりこんな感じ:
- 物価が落ち着きつつある
→ 企業にとって追い風
- 雇用環境が安定
→ 景気の急変リスクが減る
- 利下げの可能性
→ 株価にはプラス材料
SBI証券・楽天証券で口座開設
新NISAで投資を始めるには、まず証券口座の開設が必要です。初心者でも手続きは簡単で、スマホだけでも完結できます。
口座開設が済めば、すぐに少額から投資を始められます。
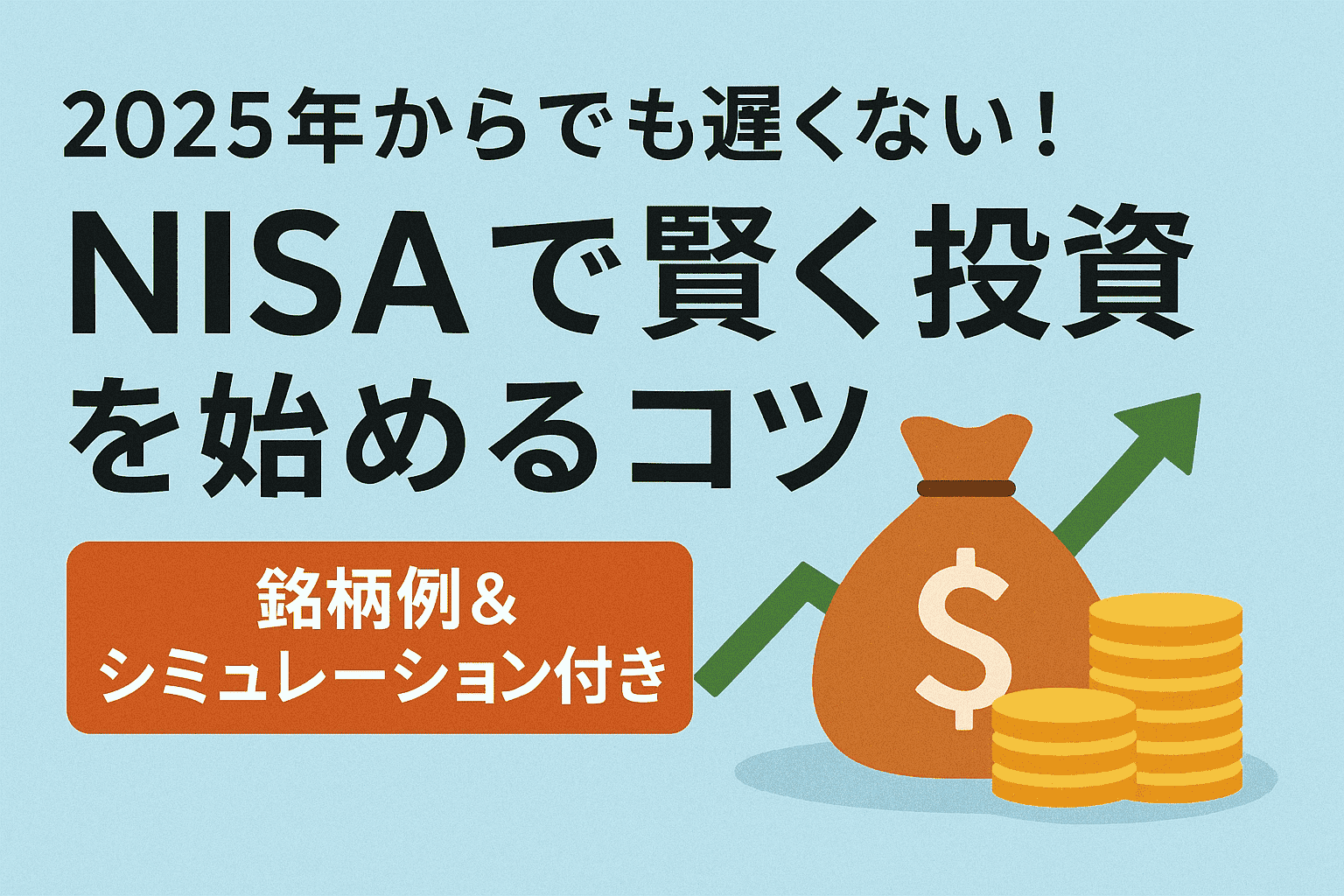

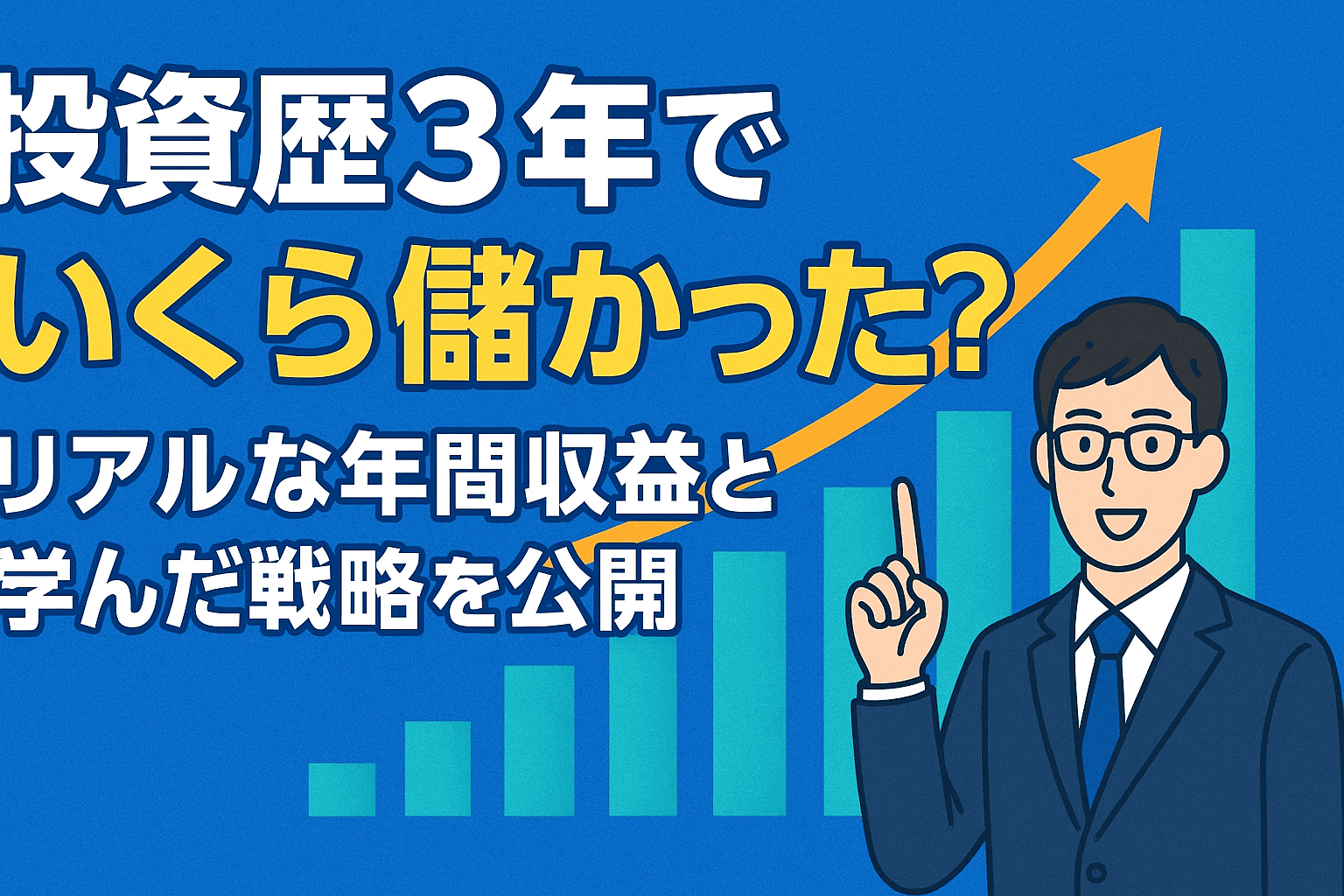
コメント