投資初心者は必見!
投資信託と株式投資の違いをわかりやすく解説します。
投資信託と株式投資、どちらがより効率的に資産運用できるのか?
また、自分はどちらが向いているのか?
投資信託と株式投資、どちらも初心者である方に向けて、分かりやすく解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
①投資信託とは?基本を理解しよう
投資信託について、まずは基本的な概要、仕組みについて解説します。
投資信託とは「投資成果をプロに託す」商品
投資信託とは、複数の投資家から集めた資金を専門の運用会社が運用する金融商品です。
つまり、運用をおこなうのは自分ではなく、運用会社です。
私たちが行うのは、商品を選択して購入、そして運用してもらうためのお金を支払うことまでです。
そこからは、運用のプロの出番というわけです。
なので、その運用した成果については、もちろんそのプロの腕次第ということになります。
投資信託のメリット
●投資信託のメリット3点!
①プロによる運用で手間が少ない
②分散投資によるリスク軽減
③初心者向けの学びやすさ
①プロによる運用で手間が少ない
先ほどお伝えしたように投資信託は、投資した投資商品の運用をプロに任せることができます。
運用をしたことがない初心者の方でも、投資信託を購入するだけで運用を行ってくれるので、とても楽ちんです!
②分散投資によるリスク軽減
また投資信託には、「分散投資」というリスク軽減策が取られています。
分散投資とは、その名の通り投資先を分散させることです。
例えば、分散投資の逆になるのが集中投資です。
集中投資とは、ある1つの投資先に資金を集中して投資することです。
この場合、その投資先企業が倒産あるいは何らかの問題が生じたときに大きく価格が下がる可能性や、元本が保証されない場合もあります。
集中投資には、このようなリスクが生じます。
しかし、投資信託は分散投資なので、そのようなリスクを軽減できます。
複数の投資先に分けているので、ある投資先の価格が下がった場合も、その他の投資先でバランスを取ることができます。
③初心者向けの学びやすさ
また、初心者にとっては、とても学びやすいです。
その理由の1つが、投資信託のシンプルな仕組みから来ています。
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を専門の運用会社が運用し、得られた利益を投資家に分配するという形です。
株式投資と違って、個別の銘柄選びや売買のタイミングを気にする必要がないため、初心者にとっては非常にわかりやすく、学ぶ敷居が低いと言えます。
また、投資信託には多くの種類があるので学びやすいです。
投資信託は、リスクを抑えた債券型から、リターンを狙う株式型、さらにバランス型など様々な種類があり、自分の投資スタイルに合ったものを選びやすいです。
また、運用のスタイルや方針に関する説明がしっかりされているため、自分に合ったものを選ぶ過程でも学びやすいです。
NISA・つみたてNISAなら ひふみ投信
投資信託のデメリット
●投資信託のデメリット2点!
①運用手数料がかかる
②運用成績に依存
①運用手数料がかかる
プロに運用してもらうのでもちろんタダというわけにはいきません。
年間で信託報酬という、投資信託を運用をしてもらうための手数料を支払わなければいけません。
この信託報酬も、投資信託の種類によってことなります。
この信託報酬は、投資信託の現時点での評価額に、(実質)信託報酬(%)を掛けた金額が毎日、自動的に差し引かれます。
計算式だと以下のようになっています。
1年間の信託報酬(概算) = 現時点での評価額 × (実質)信託報酬
具体的には、「現時点での評価額に対して年~%」という感じです。
例えば、購入した投資信託の「現時点での評価額」が100万円で、「信託報酬」が1.5%(税込で実質1.65%)の投資信託を買う場合...
信託報酬は年間で100万円×1.65%=16,500円です。
仮に1年間運用しても資産がまったく増えなかった場合、たんに信託報酬だけが差し引かれることになります。
②運用成績に依存
また、「プロが運用を行うので必ず安全で利益が出る!」というわけではありません。
投資先の企業の急な経営状況や世界情勢の変化などで、運用がうまくいかない場合もあります。
投資を行う方も、100%利益を出せる完璧超人ではありません。
しかし、今までの投資運用経験も重ね、投資の相場観なども兼ね備えているので、投資初心者にとっては運用をお任せした方が利益が出る確率は高いです。
上記のデメリットにもありますが、メリットとして分散投資やプロが運用という点を踏まえると、初心者の方にとっては、投資信託はとても理にかなっている投資商品だと思います。
特に、投資を始めたばかりの方や、大きく失敗したくない方には、投資信託をおススメめします!
②株式投資とは?基本を理解しよう
次は株式投資について、基本的な概要、仕組みについて解説します。
「企業の株を購入して成長や配当などで利益を得る」商品
株式投資とは、ある企業が発行した株式を買うことでその企業の株主となり、企業の成長に応じて報酬をいただく金融商品です。
また、株式の売却益以外にも、会社の利益の一部を還元してもらう配当、株主であることへのお礼の株主優待などもあります。
つまり、株式を売却せず保有しているだけでも自分の利益を増やしたり、恩恵を受け取ることができます。
よって、株式投資は、「企業の株を購入して、企業の成長や配当などで利益を得る」商品だと言えます。
株式投資のメリット
●株式投資のメリット3点!
①高いリターンの可能性
②配当金を得られる
③自分で運用ができる
①高いリターンの可能性
株式投資では、購入する株式の価値(株価)はリアルタイムで変動します。
つまり株式市場が開いている時間帯は、1分1秒で株価が動きます。
株式は金融商品の中でも、流動性がかなり高い(売買しやすい)です。
そのため、買いも売りもハイスピードを繰り返しおこなわれるので、株価が変動しやすいです。
しかし、その分短期間で高いリターンを得る可能性もあります。
②配当金を得られる
株式投資は何も売買だけで利益が生まれるわけではありません。
株式を保有しているだけでも利益を受け取れます。
それが、配当金と呼ばれるものです。
配当金は、「ある会社が生み出した利益の一部を株主へ還元してあげるよ」という制度です。
なぜなら、会社が設立されるときの資本金や設備投資などのお金は、投資家がその会社の株式を購入する代わりに渡される現金が元手になっているからです。
つまり、配当金は株主が受け取るべき権利とも言えます。
会社の成長を願って投資をしているので多少の報酬は欲しいですよね。
③自分で運用ができる
このメリットは、先ほどの投資信託と比較することができます。
投資信託の場合は、運用はプロに任せることができますが、逆に個人ではちょっとした運用もできないことも意味します。
投資信託という商品は、株式のセットのようなイメージです。
セット販売なので、自分で好き勝手にその中身を入れ替えたりはできません。
しかしその点株式投資では、自分で投資する銘柄を変更したりできます。
例えば...

A社とB社とC社にそれぞれ投資しているが、C社の業績が悪そうな感じだから、次はD社を購入しよう!
このように、自分で自由に組み合わせを変えられます。
自分で自由に運用できるのは、市場変化に合わせて柔軟に対応できることを意味します。
株式投資のデメリット
●株式投資のデメリット2点!
①市場のリスク
②短期的な変動が大きい
①市場のリスク
株式投資は市場リスクの影響がとても大きいです。
例えば投資信託は、個別株式を複数組み合わせたセットのようなイメージだと、先ほどご説明しました。
そのため、ある業界の動向が悪い方向に向かっている場合には、銘柄を分散しているので、保有している銘柄すべてに影響を与えるリスクを回避できます。
しかし、株式投資の場合は個別銘柄に投資しているので、市場リスクがもろにその投資している会社に影響がを与えます。
つまり、大きく株価が下がる可能性があるということです。
しかし、複数の個別銘柄に分散投資することで、投資信託のメリットと同じような仕組みにできますので、そこまで心配する必要はありません。
②短期的な変動が大きい
これはメリット①でもお伝えした、「高いリターンの可能性」とのトレードオフの関係になります。
株式市場はリアルタイムで株価が変動しますので、高いリターンを得られる反面、株価急落などのリスクもあります。
例えば、ある会社が不祥事を起こし、大きくニュースで取り上げられ、今後の業績にも影響を与えそうな可能性があれば、投資家はすぐに株式売却に取り掛かります。
ほとんどの投資家が同じように考える出来事が起これば、短期的に株価が急落する可能性も少なくありません。
また、投資金額が大きくなるほど、短期的な変動による影響も大きくなります。
特に株式投資初心者だと、短期的な変動で心理的リスクも働いて、うまく売買タイミングをつかめない方も多いです。
③投資信託 vs 株式投資:初心者に最適なのはどっち?
投資信託と株式投資のメリット・デメリットについて把握したうえで、どちらが初心者にとって最適なのかを比較していきましょう!
投資信託の選択肢
初心者が投資信託を選ぶ理由としては、以下の3点がポイントになります。
●投資信託を選ぶ理由3点!
①分散投資
②手間が少ない
③初心者向け
投資信託は圧倒的に、初心者からでも始めやすいです。
分散投資でリスクを最低限に抑え、プロに運用してもらうため手間も抑え、投資の足掛かりを築けます。
ただ、その際にかかる費用(購入・売却時にかかる手数料や運用してもらうための信託報酬)が株式投資に比べて高いです。
ですので、一番は「リスクを抑えたい!」という点を強く重視したい方は、投資信託を1つの選択肢としてよいと思います。
株式投資の選択肢
初心者が株式投資を選ぶ理由としては、以下の2点がポイントです!
●株式投資を選ぶ理由2点!
①リターンの可能性
②自己管理の自由
初心者でリターンを最優先で狙うなら、株式投資がおススメです。
ただ、その反面高いリスクもあることは覚えておいてください。
また、自分のポートフォリオ(複数銘柄の組み合わせ)を自由に管理できるので、世の中の流れや急な出来事に合わせて柔軟に対応できます。
また、手数料に関しても株式保有時には投資信託のような信託報酬はかからないので、費用負担は少ないです。
購入・売却時に手数料がかかりますが、最近は手数料無償化も進んでおり、株式投資においては手数料がほとんど発生しません。
投資信託と株式投資の比較ポイント
では、具体的に投資信託と株式投資を比較するポイントをご説明します。
①リスクの違い:投資信託 vs 株式投資
リスクはあくまでも危険性という意味なので、必ず損するということではありません。
しかし、このリスクって具体的にどのように調べればいいの?
このように疑問に思われると思います。
株式投資のリスク測定「ボラティリティ」
その場合は、「ボラティリティ」を確認しましょう。
ボラティリティ(volatility)とは「価格の変動率」のことです。
価格の変動が大きければボラティリティも大きくなり、価格の変動が小さければボラティリティも小さくなります。
つまりボラティリティが高いほど、ハイリスク・ハイリターンとなります。
私は主に楽天証券を利用していて、その投資アプリ「iSPPED」の中の機能に「スーパースクリーナー」というものがあります。
そこで過去60日ボラティリティを確認しています。
実際に確認してみると、60日ボラティリティの高い順に一覧表示ができます。
また楽天証券に並んで、口座開設数が多いSBI証券でも同じようにスクリーニング機能がありますので確認してみてください。
投資信託のリスク測定「シャープレシオ」
シャープレシオとは、主に投資信託のような商品の投資効率を数値化するための指標です。
このシャープレシオを確認することで、投資する商品のリスクとリターンを比較して、結果どの程度リターンが上回っているのかが分かります!
ちなみに、そのシャープレシオの計算式は以下のようになっています。
シャープレシオ=(対象商品のリターン-安全資産の利子率)÷リターンの標準偏差
■対象商品のリターン:トータルリターン(過去の収益を全体的にみる指標)を指します。
■安全資産の利子率:リスクが全くなかった、いわゆるゼロの時に得られた利益を指します。
■リターンの標準偏差:リターンのブレの大きさを指します。
特に標準偏差については、もっと良く知りたい方は以下のサイトを参考にしてください。https://moneyworld.jp/news/05_00097148_news
このシャープレシオが大きいほど、一般的には優れた金融商品であることを示しています。
数値で言うと、シャープレシオが1.0以上であれば優良、2.0までいくと超優良になります。
この数値を目安にして、どの投資信託にするかを選択してみてください。
②リターンの違い:投資信託 vs 株式投資
投資信託とか株式投資はどちらもリターンを得ることができる投資手段ですが、リターンについても大きく異なっています。
リターンについても両者を比較して、どちらが自分の投資スタイルに合っているのかを確認しましょう!
株式投資のリターンの特徴
株式投資の最大の魅力は、高リターンを狙える可能性がある点です。
企業の株式に投資することで、その企業の成長や業績向上に直接的にリターンを受けることができます。
特に、成長企業や新興企業の株に投資した場合、短期間で急激な値上がりを見込むことも可能です。
例えば、過去にテクノロジー企業の株(例: アマゾンやアップルなど)は、株価が急成長し、多くの投資家に大きなリターンをもたらしました。
最近だと生成AIブームで、そのAIに使用される半導体メーカであるエヌビディアはここ数年で株価が大幅に伸びています。
このように、株式投資では数倍、数十倍のリターンを期待することもできます。
しかし、高いリターンを狙う分、リスクも大きいのが株式投資の特徴です。
特定の企業や業界のパフォーマンスに大きく依存するため、企業の業績が悪化したり、市場の不安定要素が影響したりすると、株価は急落することがあります。
例えば、先ほど挙げた半導体メーカーのエヌビディア...
中国の新興企業であるディープシークという会社の生成AIモデルが、エヌビディアのものよりも低コストで高パフォーマンスを発揮するとのニュースがありました。
この衝撃的なニュースにより、エヌビディアの株価は一時18%も大幅下落しました。
このように、株式投資はリターンが大きい反面、価格変動が激しく、リスクも高い投資手段であると言えます。
投資信託のリターンの特徴
一方、投資信託は、多くの株式や債券などを組み合わせて運用されるため、分散投資が基本です。
これにより、リスクが分散され、個別の株に依存しない安定したリターンが期待できます。
特に、長期的には、投資信託が提供するリターンは株式単独の投資に比べて安定的である傾向があります。
投資信託のリターンは、株式市場全体の動向や債券市場の変動などに影響されますが、基本的には多様な資産に投資しているため、特定の企業や市場に依存することは少ないです。
なので、株式投資のリターンの特徴でも例を挙げたエヌビディアのみに影響があるような出来事があったとしても、投資信託に大きく影響を与えるリスクは株式投資を比較すると少ないです。
このため、大きな損失を避けることができるという特徴があります。
投資信託は株式投資に比べて急激なリターンは狙いにくいものの、長期的な安定的リターンを期待する人には向いています。
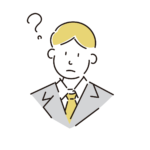
結果、株式投資と投資信託のどちらが良いの?
リターンを重視する場合、株式投資は高いリターンを狙う手段として有力ですが、その分リスクも大きく、短期的な価格変動に耐えられるかが重要です。
一方、投資信託は安定したリターンを求める投資家にとっては最適であり、特に長期的な資産形成を目指す人には向いています。
③資産運用の自由度
資産運用を行う際、投資信託と株式投資のどちらの選択において、「資産運用の自由度」も大きな要素となります。
両者の資産運用における自由度について詳しく比較してみます。
株式投資の自由度
株式投資を選択すると、大きく3つの点で自由度が得れます。
●株式投資の自由度3点!
①自分で銘柄を選ぶことができる
②売買タイミングを自分の自由なタイミングで決められる
③戦略に合わせた資産配分ができる
自分で銘柄を選ぶことができるので、投資する企業の業種などの比率を自由に決められます。

今はテクノロジーの分野の成長が著しいので、保有している飲食業の株式を売却して、テクノロジー株を多めに購入しようかな
このように、運用方法を変更する自由度が高いです。
また、株式投資はリアルタイムでの売買が可能なので、株式市場の動きに合わせて、柔軟に売買が可能です。
投資信託の場合だと、価格が公表されるのは1日1回なので、次の価格が急落した場合損を大きく被る場合もあります。
株式投資は、自分の投資スタイルや戦略に合わせて資産配分が可能です。
しかし、自由度が高いからこそ、高い情報収集能力と分析力が求められ、初心者にとってはリスクも高いことを理解しておく必要があります。
投資信託の自由度
投資信託の場合は、以下の3つの点で自由度があります。
投資信託の自由度3点!
①資先の選定がファンドマネージャー(プロ)におまかせ
②資産配分が事前に決まっている
③売買タイミングの制約
投資信託では、運用はファンドマネージャーにゆだねられます。
なので自分で銘柄を選択したりすることはできません。
また、資産配分の比率もあらかじめ決まっています。
なので株式投資と比較すると、自分の意志で資産配分を調整する自由度は限定的です。
売買タイミングについても、株式投資の自由度でもご説明した通り、株式投資と比較してリアルタイムで売買はできません。
このため、株式投資のように瞬時に売買タイミングを調整する自由度は少なく、制約があるといえます。
結果、自由度の違いは一目瞭然
株式投資は非常に自由度が高く、銘柄選定から売買タイミング、資産配分に至るまで自分の意思で運用することができます
しかし、高い自由度がある分、リスクを取る覚悟も求められます。
一方、投資信託はファンドマネージャーに運用を任せる形で、自由度は少ないです。
しかし、手間がかからず、リスクも分散されるため、忙しい人や初心者にも向いています。
④投資信託と株式投資の始め方
投資信託と株式投資を初心者が始める方法について解説します。
投資信託の場合と、株式投資の場合と分けてお伝えします。
投資信託の始め方
まずは、投資信託を行う場合の手順について解説します。
各ステップに分けていますので、初めて行う方は手順に沿って投資準備を行いましょう!
ステップ①:証券口座を開設する
●証券口座開設までの流れ
①口座開設申し込み
②本人確認書類の提出
③完了通知の受け取
④初期設定
●必要なもの
・身分証明書(運転免許証や保険証など)
・マイナンバーカード
投資信託を購入するためには、まず証券口座を開設する必要があります。
証券口座は、銀行口座のように、お金を預けて投資を行うための口座になります。
ネット証券(楽天証券、SBI証券、松井証券など)や、銀行の証券部門(例えば三菱UFJモルガン・スタンレー証券)で口座を開設できます。
口座開設までの詳しい手順は、開設したい証券会社、銀行のホームページに詳しくあります。
私はメインで楽天証券、松井証券を利用しています。
例として、口座開設については以下サイトを参考にしてみてください。
●楽天証券(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/account-flow/?msockid=1622f77d98406ae8349be72d99f76b22)
●松井証券(https://www.matsui.co.jp/event/multi-ta-02/?utm_source=microsoft&utm_campaign=shamei&utm_medium=paidsearch&argument=0p7Lzdhu&dmai=a66be9d58729fc&msclkid=a37c8c9c71f610190ba1eb260b963565)
開設後、資金を入金して、いよいよ投資信託を購入する準備が整います。
ステップ②:自分に合った投資信託を選ぶ
証券口座を開設したら、次はどの投資信託を選ぶかが重要なポイントになります。
投資信託には様々な種類があり、リスクやリターンの特徴も異なります。初心者の方には、冒頭でも伝えた以下のポイントを参考に選ぶと良いでしょう。
①リスクの度合い
投資信託には株式型や債券型、バランス型などがあります。
株式型はリスクが高めですが、リターンも大きい傾向があります。
債券型はリスクが低く、安定した運用が期待できます。
②手数料
投資信託には、運用を任せるための信託報酬という手数料がかかります。
手数料が低いものを選ぶと、長期的にリターンが増える可能性が高くなります。
③運用実績
過去の運用成績を確認して、どれくらいのリターンがあったか(トータルリターン)を見てみましょう。
過去の成績が良いからといって今後も必ず良いとは限りませんが、参考として確認してみましょう。
私としては、初心者におすすめなのは、分散投資型の投資信託です。
これにより、複数の株式や債券に投資されるため、リスクが分散され、安定した運用が期待できます。
ステップ③:少額から始める(積立投資)
投資信託は少額から始めることができるので、初心者でも安心です。
多くの証券会社では、100円や1,000円から投資信託を購入できます。
また、毎月一定額を積立てていく積立投資を利用すれば、時間をかけてリスクを分散しながら、少しずつ資産を増やしていけます。
毎月の積立額は、1万円未満でもOKです。
少額からスタートできるため、無理なく投資を続けることができます!
株式投資の始め方
次に株式投資を始めるまでの手順です。
こちらもほとんど投資信託と流れは同じになりますので、ぜひ手順に沿って始めてみましょう!
ステップ①:証券口座を開設する
口座開設の流れは先ほどの投資信託と同様で以下のようになっています。
●証券口座開設までの流れ
①口座開設申し込み
②本人確認書類の提出
③完了通知の受け取
④初期設定
●必要なもの
・身分証明書(運転免許証や保険証など)
・マイナンバーカード
投資信託と同様に株式投資を行うためには、まず証券口座を開設する必要があります。
売買手数料も無料のネット証券(楽天証券、SBI証券、松井証券など)で口座を開設するのがおすすめです!
各ネット証券の特徴について詳しく知りたい方は以下で、比較・解説しているので参考にしてください
口座を開設したら、実際に株式を購入するための資金を入金します。
ステップ②:投資資金を準備する
証券口座に入金したら、どれくらいの資金を投資に回すかを決めましょう。
株式投資は少額からでも始めることができますが、まずは生活費や急に必要となる資金を除いた余裕資金で始めることが大切です。
例えば、最初は少額(1万円や3万円など)からスタートし、少しずつ経験を積みながら増やしていくのが良いでしょう。
初めは無理なく投資を始めることが成功の秘訣です。
ステップ③:株を選ぶ
次に、どの株を購入するかを決めます。
株式投資では、購入する企業を自分で選ぶ必要がありますが、最初はどの株を選んだらよいか悩むかもしれません。
初心者におすすめの方法として、以下の選び方ポイントを参考にしてください。
①企業の業績が良い株を選ぶ
企業の成長性や安定性を考慮して、業績の良い企業を選ぶと良いでしょう。
株価が安定している企業は長期的にリターンを得やすいです。
②配当金が魅力的な企業を選ぶ
安定した配当金を支払っている企業の株を選ぶと、配当金による利益も期待できます。
③有名な企業やブランド
知名度があり、安定している企業(例:トヨタ、ソニー、ユニクロなど)の株を選ぶことで安心感を得られます。
株の選び方に迷ったときは、初心者向けにインデックスファンドという方法もあります。
これは、株価指数(例えば日経平均やS&P500)に連動した投資信託で、特定の企業に依存せず市場全体に分散投資することができます。
以下の記事では、さらに詳しく銘柄選択について深堀しているので、参考にしてください。
【投資初心者向け!】銘柄の選び方が分かるようになる。銘柄選択のルールを解説 | とむろぐ
ステップ④:株を購入する
株を購入する方法は、証券口座から「買い注文」を出すだけです。
証券口座の取引画面から、購入したい企業名や銘柄コードを検索し、株数を入力して注文を出します。
初心者向けの株式投資のコツ
①少額から始める
最初は無理なく少額で投資をスタートし、徐々に投資額を増やしていきましょう。
リスクを抑えながら経験を積むことが大切です。
②分散投資を心掛ける
株式投資では、特定の企業に依存せず複数の銘柄に投資してリスクを分散することが基本です。
③長期投資を目指す
短期間で利益を得ようとせず、長期的に保有することで安定したリターンを得ることを意識しましょう。
⑤2025年の投資トレンドと初心者向けのアドバイス
2025年のトレンドして、どのような業界、分野が伸びていくのでしょうか?
大きく以下の4つの業界が伸びていくと思われます。
①SaaS業界
②AI業界
③ヘルステック
④データ活用
また、初心者が注意すべき点とアドバイスについても解説していきます。
2025年の市場動向
2025年の市場動向を、上記に挙げたトレンドをもとに解説していきます。
最新のトレンドをつかんでおくことで、今成長している分野や領域について把握でき、投資先を絞って選択することに役立ちます!
①SaaS業界
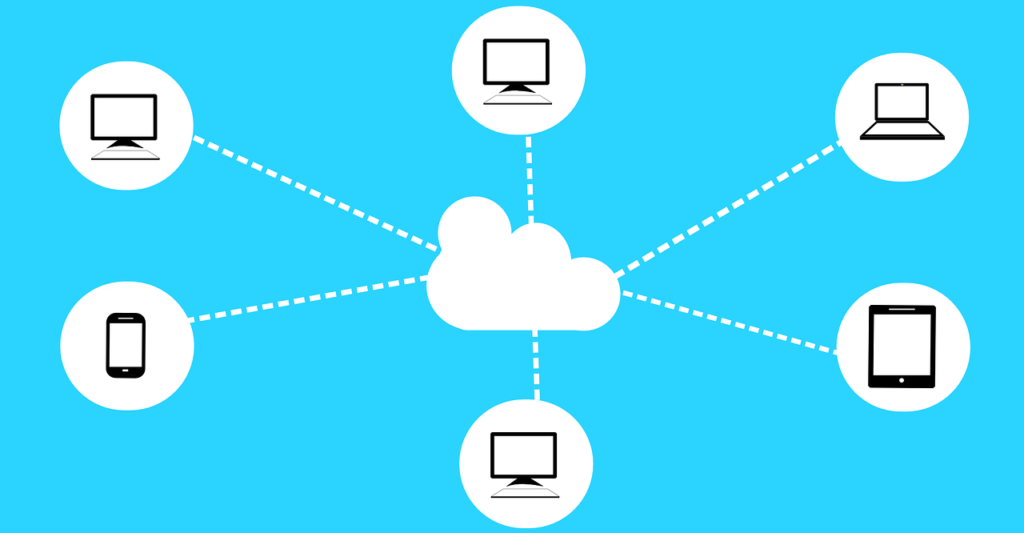
SaaS(サース)とは、クラウド上にあるアプリやサービスをインターネットで利用できるサービスのことです。
例えば、新しくパソコンを購入してワードを使用したい場合、従来だとワードのソフトを購入してパソコンにインストールしていました。
しかし、SaaSではこれらのソフトをインターネットを介して利用します。
なので、わざわざソフトを購入してインストールする手間もなく、また初期費用が高くて買えないという不便さもありません。
2025年も引き続き、SaaS(Software as a Service)業界はますます勢いを増し、企業の業務運営における中心的な役割を果たすことが予想されます。
クラウド技術の進化、リモートワークの普及、そして企業のデジタル変革への強いニーズにより、SaaS市場は今後も急速に成長するでしょう。
②AI業界
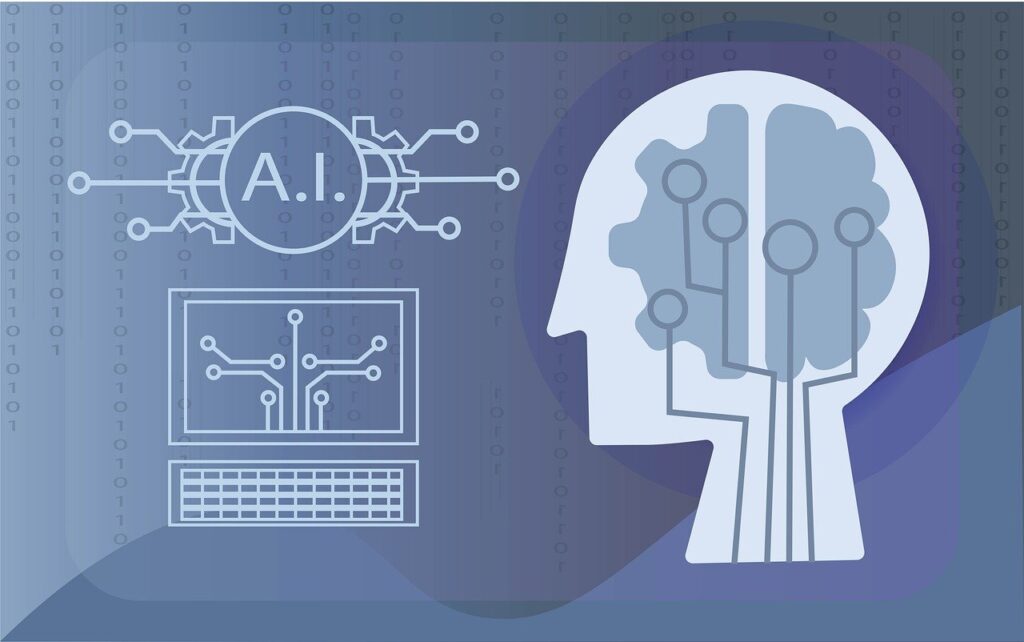
AIは言わずもがなすでに、私たちの生活にも広く浸透しています。
代表的であるChatGPTなど、新しいAIシステムが次々と開発されています。
2025年には、AIの自動化能力がさらに広がり、さまざまな業務で効率化が進むと予想されます。
特に、製造業、物流業、金融業などでのAI活用が進み、日常的な作業やルーチン業務の多くが自動化されるでしょう。
例えば、自動運転車、ドローン配送、AIによるヘルスケア診断、さらにはAIアートやコンテンツ生成など、新しいビジネスモデルが続々と登場する可能性があります。
新しいビジネスモデルが思い描かれてはいるものの、まだ開発途中であったり、AIを活用する際の規制やルールがまだ十分ではないことも成長見込みが高いと感じます。
今後は2025年以降も、急成長していく分野なので、長期投資として今の段階から投資を行っていくことをおススメします。
③ヘルステック

この業界は、上記のSaaSやAIとも特に相関性が強いため成長が期待できます。
ヘルステック(HealthTech)業界は、テクノロジーを活用して医療や健康管理を革新する分野として、近年急速に発展を遂げています。
特に、新型コロナウイルスの影響を受け、デジタルヘルスやリモート医療の需要が高まりました。
2025年には、この業界はさらに進化し、医療提供のあり方や健康管理の方法に劇的な変化をもたらすことが期待されています。
特に医療という人の命に関わる分野には、大きくのお金がかけられます。
しかし、その反面、人手不足などの課題もあります。
その課題を解消できるのが、先ほどのSaaSやAIです。
SaaSが普及することで、リモート診療の質が向上することが予測されます。
診療時間や場所に制約されない医療提供が当たり前となり、特に地方や医療資源・人でが不足している地域では、リモート医療が重要な役割を果たすことになるでしょう。
またAIは、医療画像(X線、MRI、CTスキャンなど)の解析や、電子カルテのデータ解析において非常に高い精度を発揮します。
2025年には、AIが医師の診断をサポートし、誤診のリスクを減らすだけでなく、早期発見を可能にすることで、患者の生存率を向上させると予測されています。
このように、2025年にはヘルステック業界はさらに多様化し、テクノロジーの力でより効率的で信頼性の高い医療が提供されるようになるでしょう。
先ほども言ったように、医療は人の命に関わります。
そのため今後、テクノロジーの進化に伴って、ヘルステックはさらに成長すると予想されます。
長期投資の業界としては、代表的なので初心者にはおすすめです。
④データ活用

データ活用の重要性は、ここ数年でますます高まっています。
ビッグデータやAI技術の進展により、企業や組織は大量のデータを収集し、分析する能力を持つようになり、これをどのように活用するかが競争力の鍵を握るようになりました。
上記のSaaS、AI、ヘルステックに共通している部分が、このデータ活用です。
ビッグデータは、企業の意思決定にとって不可欠な資産となりつつあります。
2025年には、膨大な量のデータを処理する技術がさらに進化し、リアルタイムでのデータ解析がより精度高く行えるようになるでしょう。
2025年には、データ活用はあらゆる分野で不可欠な要素となり、企業や組織はより効率的で効果的な意思決定を行うためにデータを活用し続けることになると思います。
あらゆる分野に共通している意思決定の基盤になるのが、このデータ活用になっているので、投資分野としては非常におススメです。
初心者へのアドバイス
2025年の投資トレンドを把握した上で、初心者の方にぜひ伝えたい投資アドバイスがあります。
①資産分散の重要性
何度も繰り返しになりますが、まずは分散投資を意識してください。
今の世界情勢はとても不安定です。
例えば、各国で起きている戦争や暴動などの地政学リスクや、米国でのトランプ大統領になり関税問題など他国を巻き込む政策リスクなどです。
正直何が起きるのか分かりません。
だからこそ、初心者の段階から資産を分散して保有しておくということを意識してください。
最近SNSでも...

FXなどの投資トレードで1日100万!

ある株に一極集中して全投資して大きく稼げました!
このように、本当かどうかも分からない情報で溢れています。
初心者は分からないことが多いからこそ、その情報を鵜呑みにして大きく損をしてしまったりするケースが多いです。
資産分散の代表例としては、やはり投資信託です。
その投資信託を選ぶ際に、先ほどの投資トレンドにちなんだものを選択してください。
株式投資を選択したときも同様に、複数銘柄に分散することをおススメします。
先ほどのSaaS、AI、ヘルステック、データ活用の4つの分けて投資することも1つの選択肢です。
②失敗しないための心構え
投資はあくまで長期目線で、しかも投資先はしっかり分散しておくことは必須です。
短期で稼げるものは「投資」ではありません。それはギャンブル性の強い「投機」です。
これまでもお伝えしてきたように、失敗しないためには、
・長期目線の投資になっているか?
・分散投資ができているか?
・投資トレンドに沿っているか?
この3つを意識しましょう。
長期目線での投資を行うことで、経済変動の波によるリスクを減らすことができ、さらに各業種企業に分散して投資を行うことで、企業の倒産リスク対策にもなります。
また投資トレンドに沿った投資を行うことで、企業の成長性も狙うことができます。
まさに資産を守りながら攻める投資が可能になります。
ぜひこの3項目は、心構えとして持っておいてください!
⑦まとめ
最後のまとめとして、「株式投資と投資信託はどっちがいいの?」という疑問に対して、私の最終的な回答をお伝えします。
投資信託 vs 株式投資の最適解
私の返答としては、初心者には投資信託をおススメめします!
なぜ初心者には投資信託なのか?
この理由としては、自分が投資をしている感覚を手軽に持ってもらうことができるからです。
冒頭にも言いましたが、投資をしていない人が投資を始めるに至るまでに一番難しいことが、自分の資金で金融商品を購入することです。
この購入するまでの段階が一番難しいのです。
それはそうですよね。
貯金しておけばほぼ減ることはありません。
しかし、実際に投資するとなると損をするリスクがあります。
その損をするリスクを受け入れたうえで、投資することはなかなか難しいものです。
しかし、投資信託には運用のプロがついています!
初心者の方は、もちろん投資未経験で運用に関する経験もないです。
なので、金融用品を購入した後は、運用のプロがしっかりサポートしてくれると考えると、この購入までのステップも乗り越えやすくなると思います。
株式投資の場合だと、投資後も自分で運用していくことが必要になってくるので、投資信託に比べて不安が大きいと思います。
また、金融商品を選択する段階で、先ほどの失敗しない心構えでも伝えた「長期目線」「分散投資」「投資トレンドに則って」、この3つをぜひ活用してください!
結論としては、初心者の皆様には投資信託をおススメめします!
そしてある程度、投資経験や雰囲気を感じてもらった後に、自分が気になる企業について調べたりして、株式投資をしていくという流れが、リスクを抑えることにもつながります。
自分のライフスタイルに合った投資方法を選ぼう!
投資経験を積んでいくと、自分のライフスタイルも考えた投資も自然と考えるようになっていきます。
実は私自身、過去にいきなり多額な資金を1つの個別銘柄にぶち込んで、大きく損失を出したことがあります。
しかし、その過去の失敗を活かして、投資方法やライフスタイルに合った投資スタイルに変えたところ、今では順調に資産を増やしています。
なので、初心者の方には無理な投資と自分に合っていない投資はおススメしません。
SNSと投資は近年での大きなトレンドにもなって、SNS上で「投資してこれだけ儲かりました!」という記事や動画を見ると、すぐにでも儲けたい!という気持ちが湧いてきてしまいます。
しかし、すぐに儲けられたとしてもそれは一時的に過ぎませんし、何の知識・経験も身に付きません。
長期目線で投資経験を積みながら、自分なりに投資について勉強して着実に資産を増やしていくことが、私は最重要だと思っています。
2025年も、私自身もこの軸だけはしっかりと守りながら、投資を継続していくつもりです。
私のブログ「とむろぐ」では、主に初心者の方向けの記事を書いていますので、他に心配や不安になることは、その他記事に詳しく書いてあります。
もしさらに気になることなどある方は、ぜひお問い合わせからご連絡ください!




コメント