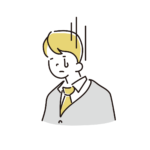
4月に入ってから日経平均株価が3万4000円まで、大急落しました...
株や投資信託を保有している方は、大打撃を受けているのではないでしょうか?
今回は以下の点に焦点を当てて解説していきます。
・日経平均株価が急落した背景
・今後の株価予想
私なりに考察してみたので、ぜひ最後までご覧ください
目次
日経平均株価が急落した背景
今回、日経平均株価が急落した最大の理由は...
大々的なニュースにもなっているので、ご存じの方も多いと思います。
理由は、トランプ大統領による「相互関税」です。
まずは相互関税について解説していきます。
相互関税とは?
他国が貿易相手国に課す関税率を、同じく課されている関税率と同じにするというものです。
例えば今回の件で言うと、米国が日本から輸入する製品に対して、関税を引き上げるという内容です。
今回の相互関税率は、「24%」と設定されました。
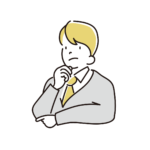
関税率についてよく知らないと、この数値が高いのか低いのかよく分かりませんよね。
現在の米国の関税率は、「2.53%」です。それが、日本に対しては、なんと「24%」にもなるのです!
この他の国々の関税率を見てみると...
・中国 34%
・ベトナム 46%
・台湾 32%
・インド 26%
・韓国 25%
・EU 20%
現在の関税率と比較すると、各国全体でとんでもない引き上げですよね!
関税が高くなると日本が受ける影響とは?
今回の相互関税率アップにより、注目を集めているのが、「自動車業界」です。
この自動車業界に含まれる、車やエンジンなどにも25%の関税が課されます。

自動車業界というと、一番有名な「トヨタ自動車」が挙げられますね!
このトヨタ自動車に対しても、相互関税の対象になっています。
世界のトヨタと言われ、日本で時価総額ナンバー1の企業が打撃を受けると、日本でトヨタ自動車の部品を生産している多数のメーカーも大打撃を受けます。
関税が課されることで、米国で車を購入する人は、関税分だけ多く支払わなければならないので、米国産の自動車への購入へと流れてしまうと予想されます。
そもそも、米国で日本車が人気なのは「低価格・高品質」だからです。
しかし、その特徴である「低価格」が失われることで、少なくとも日本車購入数は減少すると予想できます。
つまり、最終的には日本全体にもダメージが与えられるというわけです。
価格競争力の低下
自動車業界の場合は、同クラスで同種の自動車の性能、装備や各種持ち味を比較し、価格と照らし合わせた価値を指します。
関税により、この価格競争力が失われる可能性があります。
そもそも日本車が低価格で高品質なものを生産できるのは、技術力があるからです。
車以外もそうですが、日本は世界的にみても技術力が高く、その技術力が製品へと反映されています。
そのため、世界でも「日本産なら安心だ」という理由で購入されることが多いです。
しかし、相互関税の影響で単に価格だけ上がってしまえば、消費者からは技術力よりも価格面で判断されてしまうことが考えられます。
つまり価値以上の価格がついているので、他の同程度で同じ価値のものへと流れてしまうのです。
これにより、日本の価格競争力が自動車産業をはじめ、低下していく可能性があります。
日経平均株価急落までの背景
暴落の最大の原因としては、相互関税です。
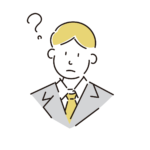
しかし、なぜ相互関税を実施するに至ったのか?
そもそも相互関税の目的としては...
あなたがうちのモノに高い関税を課すのなら、私も同じように高い関税を課します。
これが、目的としてあります。
端的に言うと、「国内産業を守る!」ことです。
米国は2024年にトランプ大統領に変わり、この米国第一主義の想いを貫いています。
私も、この考え方には不満はありません。
自国のリーダーともなれば、自国民や経済を第一優先に守るのは至極当然のことのように思います。
しかし、今回の相互関税については、米国国民に対しても影響があります。
それが大きく3つあります。
①サプライチェーンの崩壊
②国内消費の鈍化
③消費者物価指数の上昇
①サプライチェーンの崩壊
原材料の調達から、製品の製造、流通、販売までの一連のプロセスを指します。
理想を言えば、このサプライチェーンが国内のみで完結していれば、スムーズに機能して機動性のあるビジネスが展開できます。
しかし、なかなかそうもいきません。
なぜなら、原材料の調達段階で、その国からは得られないものが多数あるからです。
環境・気候の問題などで、全てのモノが自国で調達できるなんてことはありません。
例えば、チョコレートを例に挙げましょう。チョコレートの原材料の代表と言えば、「カカオ」です。
日本はカカオの輸入の8割をガーナに頼っています。
これは、ガーナの環境でしか、良質なカカオが得られないからです。
このように、国内で販売している製品のほとんどは、様々な国の製造過程を通って作られています。
しかし、関税率が上がるということは、輸入品に高い関税が付きます。
つまり材料を含めた一連の過程に関するコストが値上がりするわけです。
こうなると、今まで販売していた製品の量が減ったり、最悪の場合は生産すらできなくなってしまいます。
結果的に、関税の影響で最終的な製品価格が高くなるというわけです。
これは、サプライチェーンの崩壊を意味します。
②国内消費の鈍化
これは、サプライチェーンの崩壊から派生する影響ともいえるでしょう。
急な高い関税率を課されれば、おそらく米国内の消費は鈍化するでしょう。
消費を促されないということは、経済の停滞化にもつながります。
③消費者物価指数の上昇
また国内消費の鈍化は、消費者物価指数の上昇につながります。
米国消費者物価指数(米国CPI)は、米国国内の物価の変動を表す経済指標です。前月の指数を翌月の中旬に米労働省が公表しています。
この消費者物価指数は、投資と非常に関係があります。
米国のGDP内訳は以下のようになっています。
・個人消費:約70%、
・政府支出等:約20%
・その他:約10%
つまり、個人消費が米国内GDPに大きく依存していると言えます。
つまり、米国CPIが上がると、消費者の購買意欲の低下から、個人消費の減少につながります。
したがって、米国CPI上昇により米国経済は停滞し、株式が売られることになります。

今回の株価急落も、この個人消費が大きく減少することを予想した動きと言えますね。
株価急落は米国にも大ダメージ
今回の日経平均下落については、米国への影響も少なからずあります。
今回のトランプ大統領の相互関税開始については、トランプ自身にも大きな影響があります。
以下の記事をご覧ください。
●トランプの資産額が920億円減、「トゥルース・ソーシャル」低迷が響く
ドナルド・トランプ前米大統領の推定保有資産額は25億ドル(約3300億円)で、昨年秋の32億ドル(約4200億円)から7億ドル(約920億円)減少した。
その最大の理由は、一時大きな熱狂を生み出したソーシャルメディア事業の低迷だ。これが5億5000万ドル(約720億円)の資産減につながった。
引用:https://forbesjapan.com/articles/detail/62222
この記事から分かる通り、トランプ大統領自身の金融資産にも大きく影響を与えています。
実際に、4月現在で米国の経済指標であるNYダウも2231ドル安で、過去3番目に大きい下落幅という結果になっています。
これも、米国企業も海外にサプライチェーンを頼ってい部分があるので、大きく影響は受けるでしょう。
その予想から、株価下落につながっています。
この暴落危機をどのように乗り越えるか
今回の日経平均下落により、私が保有している金融資産についても大きく値下がりしています。
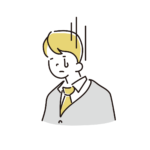
なんて下落幅だ...
下落幅を見ると不安や落ち込みもあるのですが、これは1つの買い場だとも思っています。
しかし、購入タイミングが今回の暴落では、とても難しいです。
これに似た日経平均株価の暴落が「コロナショック」の時ですね!
コロナショックの時はどうなった?
直近の大幅な下落と言えば、「コロナショック」があります。
コロナショックでは、日経平均株価は2020年3月に急落し、「16,358円」の底値を記録しました。
この急落については、過去30年間で最大の下げ幅になっています。
この急落の原因については、航空、観光業など、主に対面でやり取りするサービス業が大きく打撃を受けることが予想されたからです。
このような状況が投資家心理の悪化につながり、株式市場内で大量売りという結果になりました。
そして、今回の暴落は「コロナショックと類似性があるか?」という点が非常に重要です。
相互関税とコロナショックとの類似点
類似しているポイントは、「サプライチェーンの乱れ」です。
コロナショック時も、コロナの感染拡大を防ぐためにも接触する機会が極端に減りました。
その結果、急な物流のストップで供給が途絶えるというような事態になりました。
今回の相互関税に関しては、サプライチェーンの乱れはあるものの、急な物流ストップという事態までには発展しないことが予想されます。
しかし如何せん、経済成長を支えてきたグローバル企業の多くが、このサプライチェーンという土台に大きく影響受けることは避けられないです。

今までよりも株価が下がって買い時にはぴったりじゃない?
このように、思われるかもしれませんが、これ以上に長期的に株価が低迷する可能性もあります。
そのことを意識しながら、時期をずらして少額投資する「ドルコスト平均法」をおすすめします。
ドルコスト平均法については、以下の記事にまとめています。
https://shinzidai.com/a-basic-and-practical-guide-to-dollar-cost-averaging/
コロナショックはなぜ早期回復できた?
先ほどもお伝えしたように、2020年3月に日経平均株価が底値をつけました。
しかし、そこから4,5月には急激に回復し、ほぼ暴落前の株価に戻っています。
またそこから上昇傾向になり、徐々に日経平均株価が上昇しています。
この日経平均株価の急回復の要因は、「FRBと政府の異次元金融政策」です。
FRBとは、米連邦準備制度理事会(Federal Reserve Board)の略称で、米国の中央銀行にあたります。日本でいうと、日本銀行のような役割を果たす機関になります。
FRBが実施した政策は以下の3つです。
①3月3日にFOMCを開き、0.5%の利下げを緊急で実施した。
②さらに感染拡大が深刻化すると、3月15日に政策金利をゼロ近辺まで下げた。
③国債と住宅ローン関連の証券を大規模買い入れする量的緩和策を行った。
①3月3日にFOMCを開き、0.5%の利下げを緊急で実施した。
FRBが金融政策を決定するために開く会合のことです。
金利を下げることは、最終的に株価を上げる方向へ働きます。逆もしかりで、金利を上げれば株価は下がる傾向があります。
ここでご存じの方もいると思いますが、「株価と金利ってどういう関係があるのか?」という点についても解説します。

話を戻すと、FRBが極端な利下げ決定を行ったことが、急回復の1つの要因になりました。
②さらに感染拡大が深刻化すると、3月15日に政策金利をゼロ近辺まで下げた。
3月3日にFRBは金利を「0.5%」まで緊急利下げを行いました。
そしてさらに3月15日には、それを上回る「1%」の利下げを実施しました。
FRBの通常の利下げ幅は「0.25」ですが、コロナショックの深刻さを危惧して、思い切った政策を実施しています。
③国債と住宅ローン関連の証券を大規模買い入れする量的緩和策を行った。
国債とは、国が発行する債券のことです。国が公共事業などに必要な資金を調達するために発行されています。

国債は、投資家から資金を募る手段であり、国はその返済を約束します。
これはMBS(住宅ローン担保証券)と呼ばれています。その名の通り、住宅ローンを担保とした証券化商品のことを指します。

一言で言うと、複数の住宅ローンを束ね、それらを一つの証券として投資家に提供する金融商品です。
社会に出回るお金を増やすことを目指す金融政策になります。
この量的緩和策とは具体的に以下のことです。
・今後数カ月で米国債を少なくとも5000億ドル買い入れる
・住宅ローン担保証券(MBS)も同じく2000億ドル購入する
これにより、長期金利と住宅ローン金利を引き下げて、需要の落ち込みを最小限にする狙いがありました。
これにより市場にお金が多く流れ込むことで、投資家心理も改善しました。
この大きく3つの政策を迅速に行ったことが、コロナショックをV字回復するに至りました。
今回の相互関税はV字回復が見込みにくい
今回の暴落を受けて、4月5日にFRBのパウエル議長は、「金融政策の適切な方向性について結論を出すには時期尚早」というコメントをしています。
つまり、利下げを急がない旨を明確にしています。
しかし、トランプ大統領は高関税政策で景気後退への懸念が強まるなか、「今が利下げの好機」と圧力をかけています。
トランプ大統領も自身の金融資産は大分ダメージを受けているでしょうし、何か対策に出ることも考えられます。
FRBもすぐには利下げに踏み切らないと予想すると、投資家からの期待も薄く、株価の下落リスクはまだ高いと予想します。
さらに今回の相互関税という世界的に大きな影響を与えると予想されたことを、あえて実施したことから、今後市場も慎重になる傾向になると思います。
そうなると、V字回復についても、短期間で起こる可能性は低いと考えられます。
まとめ
下落リスクは依然高く、株価回復には時間がかかると予想します。
やはり、相互関税による大企業のサプライチェーンの崩壊が見込まれることから、悲観的な見方が大きいです。
さらに、今まで株式市場を牽引してきたAI分野も、現在は特段材料がなく逆風になっていることも要因にあります。
買い場としては、時期を見ながら少額投資するスタイルであれば、今後の下落リスクにも対応しながら投資継続できます。
私自身としても、毎月3万円ずつ投資にまわしているので、今回の下落で株価が下がった所で少額で買いを入れてきたいと思います。


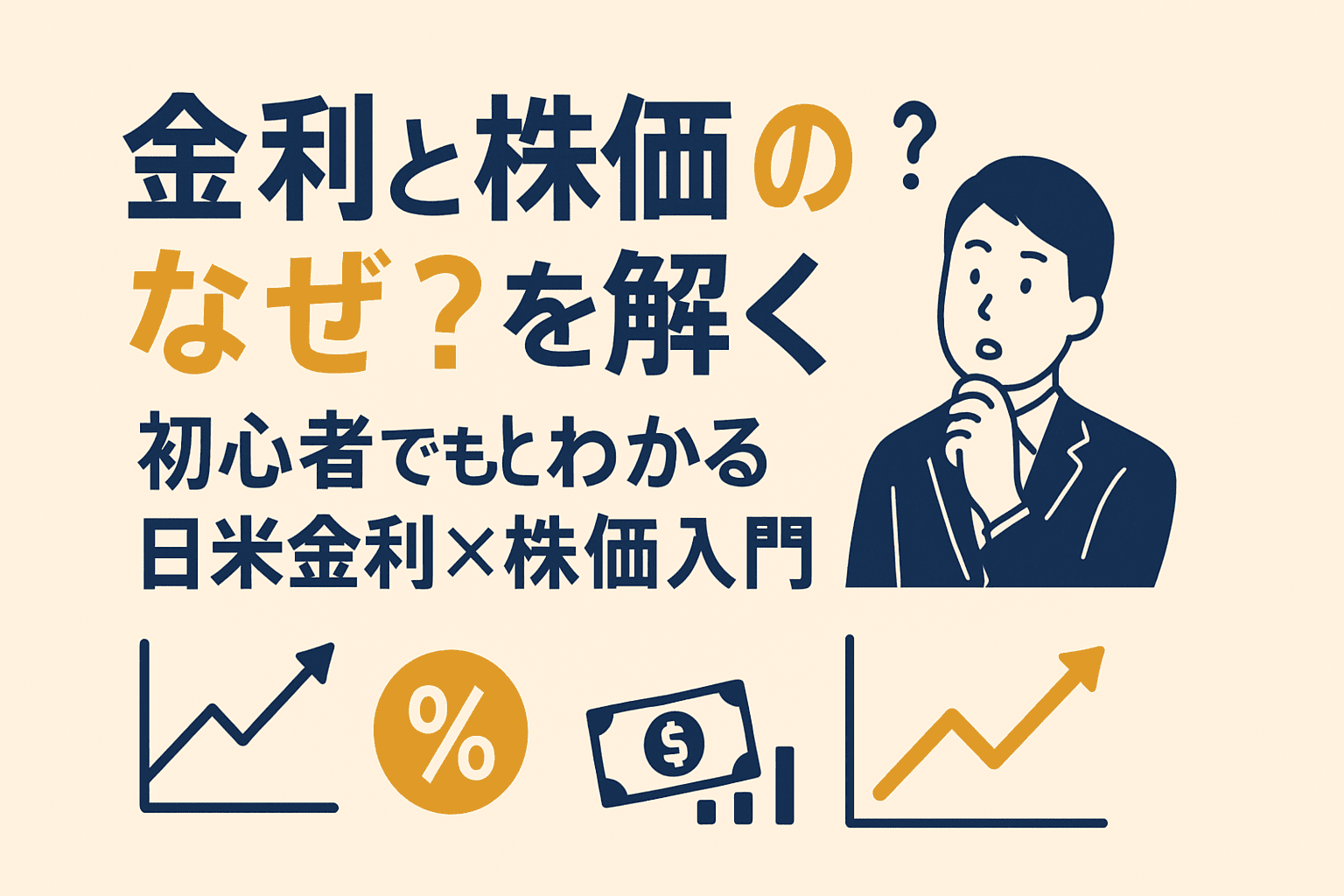
コメント